
【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2026.01.05
更新日:2025.07.28
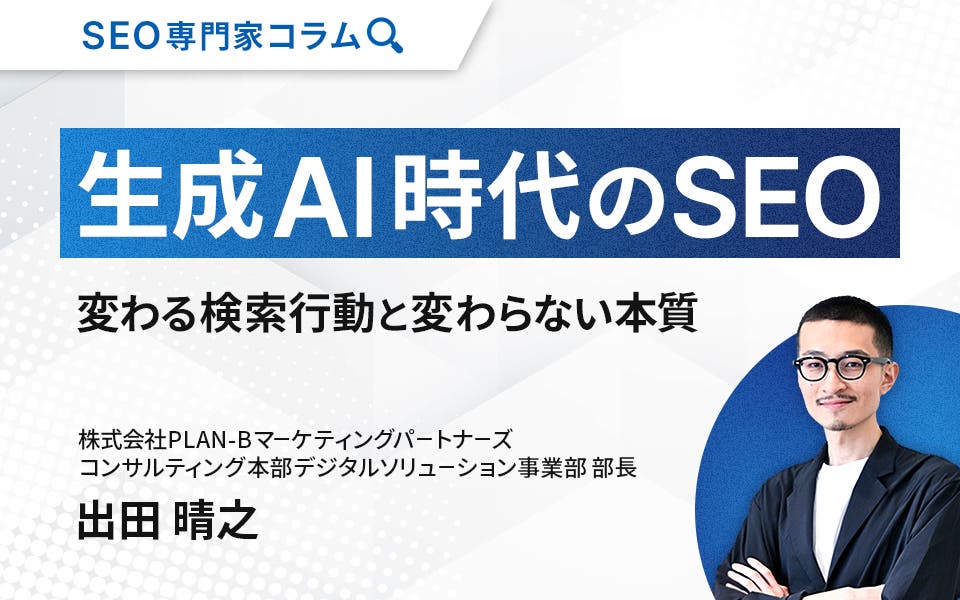
「SEOとLLMOは別物なのか?」「生成AIの台頭によって、SEOの効果は薄れてしまうのではないか?」——こうした議論が、今まさに活発に交わされています。その背景にあるのは、生成AIの急速な進化と、それに伴うユーザー行動の変化です。
しかし、SEOと生成AIは決して対立するものでありません。むしろ両者は共存しうるものであり、それぞれの特性を理解し活用することが、これからのデジタル戦略において重要だと言えます。
本記事では、生成AI時代におけるSEOの本質的な変化を捉えながら、これからどのようにSEOに取り組むべきかを解説していきます。
かつてのSEOでは、「検索結果で上位に表示されればクリックされる」という構造が明確であり、クリック率は検索順位と強く相関し、順位を上げることがトラフィック拡大の鍵でした。
しかしGoogleのAI Overviews(AIによる概要)により、ユーザーがリンクをクリックせずに疑問を解決するケースが増え、“ゼロクリック問題”として注目を集めています。
さらに、こうした変化はユーザーの検索行動全体にも影響を及ぼしています。以下に示すPRCAモデルのように、ユーザーは生成AIなどの新たな情報ツールを起点とし、検索エンジンとの間を行き来しながら、疑問を持ち、情報を調べ、比較・検討を繰り返して、最終的な行動に至るように変容しているのです。
関連記事:【専門家コラム】生成AI時代のカスタマージャーニーフレームワーク”PRCA(プルカ)”とは
実際、Bain&Companyの調査では「どのサイトにも遷移しないユーザー」が約60%に達していると報告されています。さらにStatCounterによると、2024年10月時点のGoogle検索のシェアは89.3%であり、10年ぶりに90%を下回りました。ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIが次々登場した2023年以降、ユーザーの検索行動そのものが多様化・分散し始めていることが伺えます。
こうしたユーザー行動の変化が進む中で、従来型のSEO施策だけでは十分に対応しきれない場面も増えています。もちろん、SEOは今もなお有効な打ち手であり、その重要性が失われたわけではありません。ただし、その効果を最大化するには、このような変化を踏まえた、より戦略的な設計が求められています。
このように検索行動が変容していく中で、注目されているのが「LLMO」です。LLMOとは、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)における応答結果に、自社コンテンツが取り上げられやすくなるよう最適化する取り組みのことをいいます。
検索結果に表示されることを目指すSEOとは異なり、「生成AIによる回答欄への露出」を目指すという点で、LLMOはSEOとは異なる新しい取り組みとして語られるケースもありますが、両者は別ものではありません。PLAN-Bでは、「LLMOは、SEOの延長線上にある」と考えています。
検索エンジンとLLMは、一見するとまったく異なる技術のように思えますが、Web上から情報を集め、ユーザーの「問い」に対して「適切な答え」を提示するという本質的な構造においては、非常によく似た仕組みを持っています。
たとえば検索エンジンでは、Web上から情報をクロールし、インデックスに登録した上で、ユーザーの検索意図を解析し、ランキングを計算して検索結果を生成します。一方LLMも、大量の外部ドキュメントを取得し、トークナイズとベクトル化を行って学習し、プロンプト(質問文)から文脈を理解し、最も適切と思われる回答を出力します。
つまり両者は、
という共通の流れに沿って情報を処理している点で、構造的な類似性が非常に高いのです。
| 抽象構造 | 検索エンジン | LLM |
| 1.情報を集める | クローリング | 学習用データ収集/外部ドキュメント取得 |
|---|---|---|
| 2.登録する | インデックス登録 | トークナイズ&埋め込み |
| 3.意図を解釈する | 検索意図の解析 | プロンプトの文脈理解 |
| 4.答えを導き出す | ランキング計算 | 次トークン予測 |
| 5.結果を出力する | SERPs/スニペット生成 | 回答文の生成 |
評価項目や技術基盤の観点では、LLMOはSEOの延長線上にあると言えます。生成AIも、構造的に整理され、信頼性が担保された情報を優先的に引用・要約に活用する傾向があるため、以下のようなSEO施策がそのままLLMOにも好影響を与えると考えられるからです。
したがって、SEOで蓄積してきた知見や運用ノウハウは、LLMOにも直結して活かすことができる資産であり、SEOとLLMOを分断して考えるのではなく、戦略的に一体で考えていくことが極めて重要です。
実際に、Googleが提供するAI Overviewsに関しても、検索結果に「裏打ちされた情報を提示する」と明記されており、さらには「SEOで高く評価されているコンテンツほど、AIによる回答にも引用されやすい」という相関関係が、複数の外部調査からも確認されています。
AI Overviews are built to surface information that is backed up by top web results, and include links to web content that supports the information presented in the overview.
(日本語訳:AIによる概要は、トップクラスのWeb検索結果によって裏付けされた情報を表示するように構築されており、AIによる概要で提示される情報をサポートするWebコンテンツへのリンクを含んでいます。)
出典:https://search.google/pdf/google-about-AI-overviews-AI-Mode.pdf
また、SEOとLLMOは、それぞれ異なるチャネルにおいてユーザーとの接点を創出する役割を担っており、トラフィック獲得の観点では補完関係にあります。
特に近年は、Google検索でもAI Overviewsが検索結果の最上部に表示されるようになり、ユーザーが従来の青いリンクをクリックせずに、AIの要約だけで完結してしまうケースが増えてきました。また、ChatGPTやGeminiといった生成AIを情報収集の起点とするユーザーも急増しており、「検索エンジンを利用しないユーザー層」も無視できない存在になりつつあります。
こうした環境下では、従来のSEOだけではカバーしきれない接点が確実に生まれています。LLMOは、まさにこのようなユーザー層をカバーできる施策であり、SEOでは届かない領域を補うという点で、両者は補完的な関係にあると言えるのです。
生成AIという新たな接点が登場した今、求められているのは「SEOか、LLMOか」という二項対立ではなく、従来のSEOの本質を土台にしながら、それを生成AIにも拡張するという統合の考え方です。ポイントとして、以下の3つがあります。
従来のSEOでは、「カニバリゼーションは避けるべき」という考え方が一般的でした。これは自社サイト内の複数ページが、同じキーワードや検索意図を取り合ってしまうことで、検索エンジンが「どのページを評価すべきか」判断しづらい、SEO評価が分散するなどのリスクがあると考えられていたからです。
しかし、これからのSEOでは、1つのキーワードに対して1つのページで対応するのではなく、ユーザーごとの背景や文脈を踏まえて“ニーズごとにページを分ける”という考え方が主流になると考えています。そう考える主な理由には、検索エンジンのアルゴリズムが進化してより細かな文脈を理解するようになっていること、検索結果のパーソナライズが強化されていることが挙げられます。
たとえば、「トレーニング やり方」というキーワードで検索した場合、これまでは基礎的なポイントから上級者向けトレーニングまでを網羅した包括的な記事が評価されやすい傾向にありました。しかし今は、「初心者向けのトレーニング方法」や「上級者向けの筋トレメニュー」など、それぞれのニーズにピンポイントで最適化されたコンテンツの方が、高く評価されるようになっています。
これは、検索エンジンや生成AIが「このユーザーの質問に、今最も適切に答えているのはどのページか?」という視点で情報を評価するようになってきているためです。そのため、従来のようにキーワードを軸に情報を網羅するのではなく、「誰に・どんな目的で・どんな状況で読まれるか」といった、文脈起点のコンテンツ設計が一層重要になっていくでしょう。
関連記事:【専門家コラム】キーワードのカニバリを意識する時代は終わった
これからのSEOでは、単にキーワードをもとに情報を並べるだけでは、生成AIに選ばれることは難しくなってきます。特に、AIによる戦略策定の自動化が進んでいる今、差別化の起点となるのは“問いの立て方”そのものです。
従来は施策を人がExcelやPPTでまとめていたのに対し、今は生成AIがrawデータを処理・分析し、施策のアウトラインを作る時代へと変わりつつあります。だからこそ、人が担うべきは「問いを立てる思考」への集中です。
たとえば、
といったように、“他社と違う問い”を起点に施策を立てることで、生成AIにとっても価値ある情報源として認識されやすくなります。つまり、これからのSEOでは、誰よりも深く・広く問いを立て、独自の視点で答える力こそが、「選ばれる理由」になるのです。
関連記事:【専門家コラム】整いすぎた世界に抗う – “独自性”で個を貫くコンテンツ論
これまでは「Googleに自社サイトを最適化」することがSEOの中心でした。しかし、生成AI時代のSEOでは「Web上にある自社情報すべて」を最適化していく発想が必要です。なぜなら、生成AIは、Web上に存在するあらゆる情報を元に回答を生成しているからです。
実際、ある人物についてWeb上に情報が多く掲載されていれば、それなりに正確なプロフィールが生成されますが、情報が少なければ事実と異なる内容が出てくることもあります。つまり、Web上に自社情報が十分に存在しない場合、AIによって不正確なイメージが広まったり、本来届けたいメッセージとは異なる形で解釈されたりするリスクが高まるということです。
だからこそ、生成AIに正しく認識・引用されるための情報発信戦略を立てることが求められます。自社サイトにとどまらず、外部メディアやニュース記事、Q&Aサイト、SNS、プレスリリースなど、多様なチャネルを通じて自社の存在や強みをWeb上に可視化しておくことが大切です。
生成AIの登場により、従来のSEOだけではカバーしきれない接点が増えつつあります。こうした環境の中で重要なのは、“SEOとLLMOの本質的な共通点”を理解し、検索体験やAIによる変化を前提とした情報発信に切り替えていくことです。
つまり、これまでのSEOで培ってきた“ユーザー中心の情報設計”という本質を見失わずに、それを生成AIという新たな接点にまで拡張していく、という考え方です。
SEOもLLMOも、最終的に目指すべきは「ユーザーの問いに、最も適した答えを届けること」に変わりはありません。その実現のために、私たちは技術や仕組みの変化を正しく捉え、発信の方法と接点を進化させていくことが求められます。