
SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2025.06.27
更新日:2024.03.13
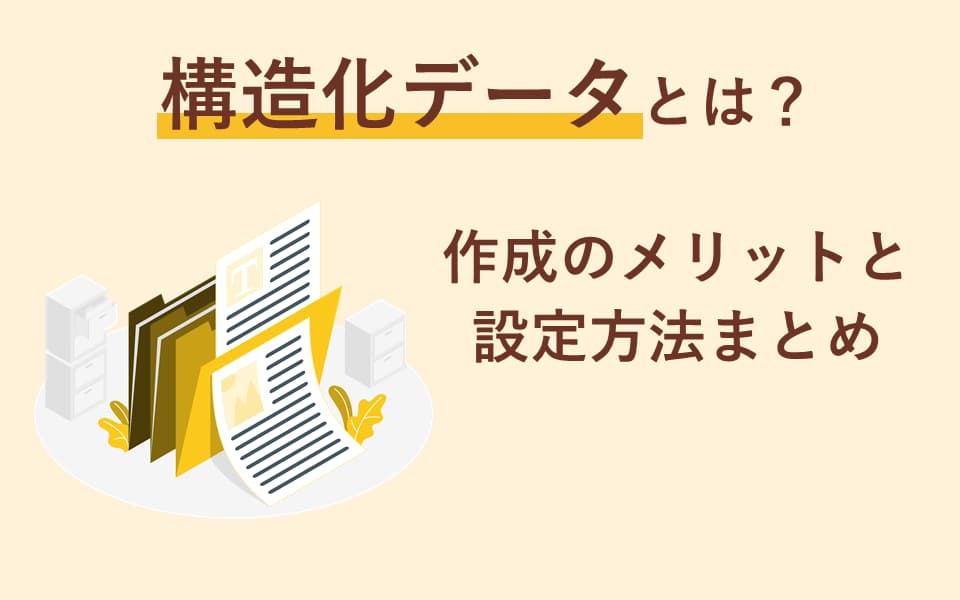
編集部注:2024年3月13日にリンク切れを修正しました。
自社サイトでも構造化データを作ろうと思っても、構造化データ自体のことも構造化データの作り方もよくわからないということがあります。
構造化データとは、Webサイトの情報をコンピューター(検索エンジン)に理解してもらえるように決められたルールのもとで作成したデータのことです。
構造化データがあることで、検索エンジンがWebサイトの情報を正しく認識し、検索結果にリッチスニペットとして表示されることができるようになるのですが、よくわからないという人が多いです。
この記事では、構造化データについて紹介します。

構造化データとは、HTMLで書かれたWebサイトのデータをタグ付けしたものです。タグ付けすることによって、検索クローラーがWebサイトのデータを正しく認識しやすくなります。
たとえば、Webサイトにこのような情報が記載されているとします。
<div>
Webサイト名:PINTO!
運営者:PLAN-B
サイトアドレス:https://www.plan-b.co.jp/blog/
</div>
私たち人間は、この情報をみて
と認識できますが、検索クローラーにとってはこの情報は単なる文字列でしかありません。
この認識を「単なる文字列」ではなく「PINTO!はサイト名」「PLAN-Bは運営会社」「https://www.plan-b.co.jp/blog/はサイトアドレス」としてもらうために必要なのが、タグ付けされた構造化データなのです。
構造化データについて調べると必ず一緒に論じられるセマンティックWebとは構造化データと同じく、人間が文字列を見てその情報がなんなのかを判断するように、コンピューターもその情報がなんなのかがわかるような仕組みのことを指します。
Webサイトを構造化データ化するということは、セマンティックウェブの一部ということになりますね。

構造化データは、検索エンジンがWebサイトに書かれている内容を正しく認識するために必要なことでした。では、Webサイトを構造化データにするメリットはなんでしょうか。
Webサイトの構造化データを作るとSEO対策になるといわれているのです。具体的には以下の2つの大きなメリットがあります。
Webサイトの構造化データを作ることで、検索エンジンがWebサイトのコンテンツを正しい状態で認識しやすくなります。
正しい状態とは、先程のこの情報を
<div>
Webサイト名:PINTO!
運営者:PLAN-B
サイトアドレス:https://www.plan-b.co.jp/blog/
</div>
以下のように単なる文字列として認識するのではなく
Webサイト名:PINTO!運営者:PLAN-Bサイトアドレス:https://www.plan-b.co.jp/blog/
下のように人間と同じように分類して認識するということです。
Webサイト名はPINTO!
運営者はPLAN-B
サイトアドレスはhttps://www.plan-b.co.jp/blog/
このように認識してもらうことで、Webページで言及された場合や他のWebページで同じ分類の文字列が出た場合の比較が容易になります。
検索ユーザーが検索した場合も「この情報を検索しているなら、この分類の情報が役立つから、あのサイトの中から情報を出そう」のようになりやすくなることが期待できるのです。
検索エンジンが、Webサイトの情報を正しい分類のもとに認識してくれるようになると、WebサイトやWebページがGoogle検索結果の「リッチスニペット」「ナレッジグラフ」のような特殊な検索結果表示に出現しやすくなります。
アンサーボックスと呼ばれるこれらの特殊な検索結果表示は、検索ユーザーの目につきやすく、クリック率も高いのです。
リッチスニペットとは、検索結果画面に表示される視覚的な情報がメインの情報のことです。ユーザーが入力した検索キーワードに関連する画像なども表示されます。
ナレッジグラフは、Google検索画面の右上にボックス状になって表示される情報ボックスのことです。たとえば、会社名を指名検索した場合、その会社の「会社名」「所在地」「GoogleMap情報」「会社の外観」などが表示されますが、それがナレッジグラフです。

SEO対策としても注目されているWebサイトの構造化データ化ですが、導入が必要かどうかは、自社サイトが構造化されているかどうかを確認してから決めましょう。
自社サイトが構造化されているかどうかの確認は、「Google Search Console」で確認できます。
確認方法は、
です。
Google Search Consoleでエラーが発生しているなら構造化されていないか、されていても正しくクロールされていない可能性があります。主なエラーはこの2つです。
Google Search Consoleの使用方法についてはこちらの記事もご覧ください。
「このサイトでは構造化データが見つかりません」というデータが出現している場合は、
などの原因が考えられます。
特に構造化データを作成した後にこのエラーが出現すると焦ってしまいます。しかし、構造化データを作成しても、クローラーが巡回してくるまでには時間がかかります。数時間であることもありますし、数日であることもありますので慌てないようにしましょう。
「エラーが発生したアイテム」が出現した場合は、「〇〇がありません」のようにどこにエラーが発生しているのかも記載されているので、それを参考にエラーを潰していきます。
多くの場合は「必須プロパティが入力されていない」のでエラーが発生してます。
原因としては、新しく導入したプラグインやテーマの構造化データに問題があるケースなども考えられますよ。
Google Search Consoleでは、Webサイトの構造化データに問題が生じた場合はメールで連絡がきます。しかし、現在の構造化データが悪化した場合はメール連絡がきません。自社サイトが構造化データになっていても、定期的に構造化データのチェックはしておいた方がいいでしょう。

Googleでサポートされている構造化データの形式は3つあります。
リッチリザルトを表示できるようにするには、この3つのうちいずれかを選択してWebサイトの構造化をする必要があります。3つのうち「JSON-LD」がGoogleで特に推奨されている形式です。
実際に構造化データを作る際は、Googleが推奨している「JSON-LD」を使うといいでしょう。
Googleが推奨しているJSON-LDは、見た目にわかりやすいので、検索エンジンだけでなくコードを見た人間にも視覚的にわかりやすい特徴があります。
HTMLソースとは別の場所に書くことができるので、HTMLに変更を加える必要がなく、変更があった場合にも探しやすいです。
現在の構造化データが、Goolgeが公表している「技術に関するガイドライン」に準拠しているかどうかは、
で確認することができます。

自社サイトの構造化データの作成を外注する場合は、作成にかかる工数や費用、時間を考えて判断しましょう。
料金例として
のようにWebページ1枚もしくは、1カテゴリあたりの料金になることが多いのです。
既存サイトを構造化する場合は、予算とも相談しながら検討したほうがいいでしょう。

構造化データをマークアップする方法は2種類あります。マークアップとは、記述された内容をコンピューターに理解させるために決められたルールに従って記述することです。今回の場合は、「構造化データを作ること」と言い換えて差し支えありません。
構造化データを作成する方法は、
の2つです。
Googleで推奨されている「JSON-LD」を使うものとして説明します。
HTML上で直接マークアップする方法では、HTMLにJSON-LDを直接記述していきます。JSON-LDは、HTMLコードとは別の場所に記述することが可能ですが、コードの書き方を理解した上で記述しないと構造化データがうまく読み取ってもらえずエラーの原因になってしまいます。
JSON-LDのマークアップは、scriptタグの中に記述します。Javascriptが起動するわけではないので安心してください。
つまり、
<script type=”application/ld+json”>
{
ここに記述する
}
</script>
ということです。
たとえば
を記述すると
<script type=”application/ld+json”>
{
“@context”: “https://〇〇▽▽.org/”,
“@type”: “Recipe”,
“name”: “バナナスコーンのレシピ”,
“description”:”ページ概要”,
“image”:”バナナスコーンの画像のURL”
}
</script>
のようになります。
「自分でHTMLに記述するのはできればやりたくない」と感じた人は、データハイライターを利用しましょう。
データハイライターは、Googleが提供しているツールの1です。Webサイトの構造化のデータをGoogleに伝えるために使います。マウス操作だけで簡単に使えるので便利ではあるのですが、多少の制限があるので注意が必要です。
データハイライターは、クローラーがクロールしたページにしか使えません。新しいページやページ内容を変更したばかりのページの場合は、クローラーが回ってきていないので使用できないのです。
また、サポートされるデータタイプに制限があります。データハイライターでサポートされるデータは以下の9つです。
これら以外のデータタイプを取り扱う場合は、データハイライター以外の手段を使いましょう。
CMS(コンテンツ管理システム)は、構造化データを作成するのに便利なツールです。CMSを使用すると、データを効率的に管理し、簡単に構造化データを作成できます。
例えば、WordPressなどのCMSを使用すると、ブログ記事やウェブサイトなどを簡単に構築できます。また、プラグインを使用することで、構造化データを作成するためのさまざまな機能を追加することができます。CMSを活用すれば、構造化データの作成を効率的に行うことができるため、知識がない場合には導入したほうが良いでしょう。
最後に、ユーザーにとって価値の高いサイトを制作するためのコツについて4つ紹介します。
サイト構造を整えることは、ユーザーにとって価値の高いサイトを制作するために重要なことです。まず、サイトのナビゲーションを見やすく、わかりやすくすることが重要です。
サイト内のリンクが見やすく、ユーザーが目的のコンテンツにたどり着けるようにしましょう。例えば、ヘッダーにサイト内の主要なカテゴリーを表示し、フッターにサイト内のサブカテゴリーを表示するなどの工夫を凝らすことで、ユーザーが閲覧しやすいサイトを作れます。
ユーザーにとって価値の高いサイトを制作するためには、有用な情報を提供することが重要です。そのため、まずはサイトのコンテンツを充実させる必要があるでしょう。サイトには、価値の高い情報を提供するために動画、画像、箇条書きなどの情報を含める必要があります。
また、見やすく、使いやすいデザインを採用することで、ユーザーがサイトを使いやすくなります。例えば、サイトのナビゲーションを明確にすることで、ユーザーがサイト内のコンテンツを簡単に見つけられるようになります。
ユーザーにとって価値のある充実したものを作ることで、より多くのユーザーに見てもらえるサイトを作れるでしょう。
内部リンクを使用して、ユーザーがサイト内のコンテンツを簡単に移動できるようにすることは、ユーザーにとって価値の高いサイトを制作する上で重要なポイントです。
具体的には、各ページのコンテンツを関連するコンテンツへのリンクを設定することで、ユーザーがサイト内を探索しやすくなります。また、サイト内のコンテンツをカテゴリーごとに分けることで、ユーザーがサイト内のコンテンツを探索しやすくなります。
モバイルフレンドリーなデザインを制作することで、ユーザーにとって価値の高いサイトを作成することができます。モバイルフレンドリーなデザインとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスでも使いやすいようにデザインされたサイトのことです。
サイトの全体的なレイアウトやフォントサイズ、ナビゲーションなどを見直し、モバイルデバイスでも使いやすい形にすることで多くのユーザーに見てもらいやすくなります。
また、画像や動画などのコンテンツも、モバイルデバイスでも表示しやすい形式に変換するなどの工夫が必要です。例えば、画像をリサイズしたり、動画をストリーミング形式に変換したりするなどです。モバイルフレンドリーなデザインを制作することで、ユーザーにとって価値の高いサイトを作成することができます。
構造化データを作成すると、検索エンジンが自社サイトの細かい部分まで理解してくれるようになり、SEO対策としても有利に働くことが期待できます。
構造化データはよくわからないという人も、まずは一部でもいいので正確なデータを送れるように作ってみてはいかがでしょうか。
Googleも
完全でないデータ、不正な形式のデータ、不正確なデータを含む多数の推奨プロパティを提供するより、少数であっても完全で正確な推奨プロパティを提供するほうが重要
と公表しています。
マークアップやJSON-LDなど、専門用語も出てきますので急いでいる場合は専門家にお任せするのも手ですよ。