
SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2025.07.15
更新日:2024.12.19
E-E-A-Tとは、検索品質評価ガイドラインで定められているWebサイトの評価要素で、Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった略語です。
近年のSEOにおいては、コンテンツの品質がますます重要視されるようになってきていますが、E-E-A-Tはその中でも特に注目されており、SEO従事者なら絶対に知っておくべき概念といえるでしょう。
この記事では、E-E-A-Tの基本から、E-E-A-Tを意識したWebサイト運営方法について詳しく解説します。
E-E-A-TとはGoogleのGeneral Guidelines(検索品質評価ガイドライン)で定められているWebページやコンテンツ品質を評価するための要素で、以下の4つの要素から成り立っています。
特に留意したいのは、Trustworthiness(信頼)の位置づけです。
E-A-T時代は専門性・権威性・信頼性の3項目が並列に掲げられていましたが、現在では経験・専門性・権威性の中心に信頼性が位置しています。つまり、Googleが最も重視しているのは「その情報が信頼できるかどうか」だということです。
では、具体的にはどのような点に注意してWebサイトを運用すればよいのでしょうか。それぞれの項目ごとに、詳しく解説します。
Experienceとは、「経験を元に作成されているかどうか」を評価する指標です。ちなみに、Google検索セントラルでは以下のように記述されています。
実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。
たとえば、確定申告書の正しい記入方法を知りたいときには、会計の専門家が作成したコンテンツを参照したいでしょう。一方で、確定申告ソフトの評価を知りたいのであれば、その種のサービスを体験した人たちが集まるフォーラムの議論など、別の情報を探すのではないでしょうか。
出典:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加|Google検索セントラル
例えば、デジタルマーケティングの情報を発信する本メディアPINTO!で言えば、SEOの実施経験がない人が執筆した記事は情報に深みが出ず、何を厚く書くべきかや知りたい情報は何かなどの精度が高くありません。そのようなメディアであれば、経験のある人がコンテンツの作成に携わり、コンテンツ品質を担保する方が、ユーザーにとって有益なコンテンツになるはずです。
専門性はその名の通り、サイトあるいはWebページが「ある分野においての専門的な情報を提供できているのか」を評価する指標です。専門性について考えるときは、「サイト単位」と「ページ単位」で考えるとわかりやすいです。
特定の分野に特化したサイトにすることで、専門性の高いサイトと認識されることを目指します。具体的にできることの例は次の通りです。
もし運営しているサイトが初期段階の場合は、何らかの分野に特化して記事を作成し「この分野についてならこのサイト!」とユーザーに想起されやすいメディアを目指すことをおすすめします。様々な分野を扱っている場合は、ドメインを分けることも検討するとよいでしょう。
コンテンツ作成時にも、専門性を担保することが大切です。たとえば、資産運用の記事であれば、専門的な知識や実務経験を持つ人が執筆した記事のほうが、ユーザーの信頼を得やすくなります。
つまり、上位に来ているサイトを真似たようなコンテンツではなく、「そのトピックに詳しい人が執筆、または監修をする」ことが大前提ということです。
なお、Googleは、専門性を評価するチェックリストを以下のように設けていますので、自社サイトと照らし合わせてみてください。
- コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。
- コンテンツを制作しているサイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。
- このコンテンツは、確実にトピックを熟知している専門家または愛好家によって執筆され、レビューされていますか。
- コンテンツに明らかな事実誤認はありませんか。
専門性が高くなると、サイトを訪れる人が増えるだけでなく、訪れたユーザーがサイトに滞在する時間が長くなるなど、間接的なSEOへの効果が期待できます。
💡注意点
専門性が高い内容について記事を作成する際は、ユーザーにとってわかりにくい記事になりやすいため、注意が必要です。Webを使って情報収集する層は、比較的「ライトに情報を得たい」という層が多いので、基本的には専門用語の多用には十分注意を払って、初心者にもわかりやすい平易な表現を心がけましょう。(ただし、ニッチで専門性の高い情報を求めているケースもあるので、対策キーワードによって使い分けるとよいです。)
権威性とは、「他者からの信頼を置けるメディア・コンテンツ発信者と見なされているかどうか」という指標です。権威性は別サイトからのリンクの質と量などから、判断されると言われています。
権威性の観点でしばしば例として出されるのは、お医者さんです。素人に「あなたは風邪をひいています」といわれるより、お医者さんに風邪を引いているといわれた方が、たしかにそうだなと感じますよね。Webサイトについても同じことが言えます。
他サイトにたくさんリンクを張られているサイトは、それだけ有益な情報が記載されていると判断され、Googleからの評価が高まります。たくさん引用される論文が高い評価を受けているのと同じ原理です。
「このサイトが出している情報だから正しい/信頼が置ける」とユーザーに感じてもらうには、他社サイトに引用されるような質の高いサイトコンテンツを充実させるだけでなく、長期的なサイト運用などの観点も必要になってきます。
信頼性とは、ユーザーがその情報を信じられるかという観点です。前半の図でも示したように、信頼性はE-E-A-T全体を支える基盤のような役割を果たしています。
どれだけ専門性や権威性を示しても、信頼性が欠けるとユーザーや検索エンジンからの評価は得られません。したがって、特に力を入れるべき要素といえます。
例えば、
などが観点として挙げられます。特に法律や不動産関連情報などのトピックは社会情勢に左右されやすいため、常に最新のデータで記事コンテンツを作成することが鉄則です。
常に最新情報をキャッチアップし、サイト更新を行っていきましょう。
E-E-A-Tがガイドラインに追加された背景には、医療や健康に関する情報の精度が低いコンテンツが大量に生産され、ユーザーに誤った情報が提供されるリスクが高まったという事情があります。
専門知識のないライターによるエビデンスに欠ける記事や、健康被害につながりかねないような誤った医療情報など、今でいう「低品質コンテンツ」が数多くネット上に公開されていたのです。
E-E-A-Tがガイドラインに追加される以前は、このような低品質なコンテンツでも上位表示される状況が続いており、問題視されていました。この状況を改善すべく取り入れられたのが、E-E-A-T(当初はE-A-T)のガイドライン追加だったのです。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ作成を行う際は、こうした背景や理由があることをしっていると、それぞれの項目が重視されることへの理解も深まることでしょう。
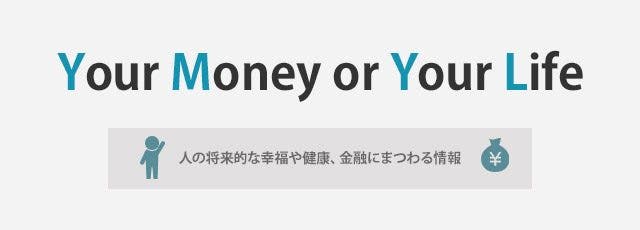
YMYLとは(your Money or your Life)の略で、人の将来的な幸福や健康、金融にまつわる情報のことを指します。例えば以下の領域です。
これらの領域は、特にE-E-A-Tを満たしているかが問われます。なぜなら、もし仮に嘘の情報が出回った場合、ユーザーの生活に大きな損害を与える可能性が高いからです。
そのため、YMYLのジャンルのWebサイトを運用している場合は特に、特にYMYLに関連するサイトを扱う場合、専門家に監修をお願いするなど、専門性・権威性・信頼性が保たれているかどうかを厳しくチェックすることが大切です。
国内のみ適用されたと言われている「健康アップデート」と呼ばれる、異例のアップデートが適用されてから、YMYLが日本でも大きく取り沙汰されるようになりました。この背景にはひと昔前まで、日本国内のYMYLに該当するWEBメディア・コンテンツ内で、根拠がない情報があふれていた時期があったためとされています。
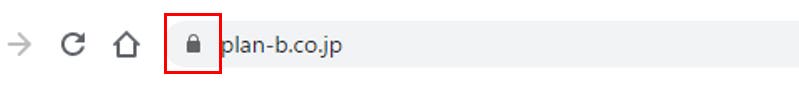
サイトをHTTPS化を使用することで、画像のように鍵マークが表示され、サイトとユーザー間の通信が暗号化されます。これにより、個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータが保護されるため、ユーザーに対して安全で信頼できるサイトであることを示すことが可能です。
このように安全な通信を行っていることを示すHTTPS化は、サイトの「信頼性」を高めるための重要な施策です。昨今サイバーセキュリティの重要性が叫ばれている中で、SSL化通信がされていないECサイトなどがあれば、Googleだけでなくユーザーとしても、サイト利用に不安を感じて離脱してしまう恐れがあります。
SSL化については、下記記事も執筆していますので、併せてご確認ください。
コンテンツが最新の情報であることは、そのサイトの信頼性に影響します。
例えば法律に関するトピックを扱うメディアの場合、法改正されても情報が古いままであれば、ユーザーはそのサイトの情報を信頼できません。最悪の場合、誤った情報が原因でユーザーに不利益が生じる可能性もあります。
扱うトピックにもよりますが、E-E-A-Tを高めるには常に最新の情報を保つように心がけましょう。
コンテンツ作成時には、情報源を明記することで信ぴょう性が増します。
例えば、ただ単に
「スマートフォンの利用者は増えています」
と書かれているよりも、
「総務省が行った調査によれば、スマートフォンの利用者は2021年時点で88.8%であり、10年前と比較すると60%近く増えています。」
と情報元のリンクと一緒に示されている方がその情報を信頼しやすいですよね。
このように、周知の事実であっても具体的な情報源を示すことでコンテンツの印象は大きく変わるのです。コンテンツ作成時には、信頼性の高い研究や専門家の意見を引用し、その出典をしっかり明記することで、信頼性を高めることが可能です。
Googleが重要視するコンテンツの「専門性」を高めて、「信頼性」の高いサイトにするためには、その道の専門家の知見を活用したコンテンツとすることが有効となります。
例えば、頭皮に関する悩みに関する記事であれば、
の取材を通じて記事執筆の上、監修者をコンテンツに掲載することはコンテンツの専門性強化に有効です。
サイト内で扱うテーマが狭くなればなるほど、専門性は高くなると考えられます。これは、例で考えてみると分かりやすいです。
上記のケースでは、例①が教育という大トピックの中で勉強法を掲載しているのに対して、例②では勉強法に特化しているため、Googleから見るとサイトとしての専門性は例②の方が高くなると考えられます。専門性特化の観点では、「広く浅く」よりも「狭く深く」の方が高めやすいといえます。
執筆者や監修者が業界内で権威のある人であれば、プロフィールページを作成し、権威を示す内容を記述します。
例えば、
など、情報を充実させることをおすすめします。
業界内で認知度が高いと、その分野で信頼されている専門家として見なされやすくなります。例えば、以下のような施策が該当します。

E-E-A-TはYMYLジャンルの順位付けに大きく関係があることから、特定のアルゴリズムを持つものだと勘違いされることも少なくありません。しかしE-E-A-TはあくまでもGoogleが提唱する検索結果の品質を評価するためのガイドラインです。
ですので、「専門家が執筆していることを明示できない」「情報源を明記していない」からといって、直接的に評価が下げられるというわけではありません。またE-E-A–Tに関する、明確なスコアリングなども存在していません。Googleも、これらのガイドラインがランキングに直接影響することはないとしています。
とはいえ、コンテンツの内容や品質を評価する基準項目となっており、間接的に影響を与えるものであることは確かです。情報発信を行う場合は、ユーザー目線でとらえ、どのように伝えれば信頼を高められるのか、またユーザーに不安を与えることなく正しく情報が伝えられるのかを意識するようにしましょう。
ここまでSEOで高評価を得るために重要なE-A-Tについて解説しました。
新しいコンテンツを作成するだけでなく「既存のコンテンツを見直して、加筆修正を行っていくこと」が非常に重要です。
分析をきちんと行い、成果が出ていないコンテンツを修正し続けることで、成長を続けるWebメディアを創ることができます。ユーザーやSEOから高い評価を受ける記事コンテンツは、一度作って終わりではありません。
メディアを伸ばそうと考えるなら、記事のリライトは行い続けるべきです。