
【2026年版】SEOとは?初心者向けに具体例や事例を紹介
SEO対策
最終更新日:2026.02.05
更新日:2025.07.29

現在のSEOでは、「ユーザーの利便性を最優先するコンテンツやWebサイト設計」が最も重要とされています。しかし、こうした価値観が確立されるまでには、数々の試行錯誤と、Googleと“検索順位を操作しようとする勢力”とのせめぎ合いが繰り返されてきました。
この記事では、検索エンジンの黎明期から現在に至るまでの主要なGoogleコア アルゴリズムアップデートとSEOの変遷を振り返りながら、「どのようにして、“現在のSEO”が形作られてきたのか?」を紐解いていきます。
検索エンジンは数多くありますが、SEOといえばGoogle向けに行うものというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
かつてインターネットの世界には多くの検索エンジンが存在し、それぞれが独自のアルゴリズムを持って競い合っていました。中でもYahoo!は、日本国内で特に高いシェアを誇る主要な検索エンジンの一つでした。
しかし、Googleが革新的な技術とともに登場し、検索精度の高さなどからシェアを拡大させていきます。
Googleは次第に勢力を強め、それまで主要な検索エンジンであったYahoo!も、やがてGoogleのアルゴリズムを採用するようになります。これにより、現在では実質ほとんどの検索エンジンでGoogleのアルゴリズムを使っている状態となりました。
事実、2025年3月時点のデータでは、1位のGoogleは約80%、2位のYahoo!は約9%のシェア率であり、約9割のシェアをGoogleが占めていることになります。
| 順位 | 検索エンジン | シェア率 ※()内は前年同月比 | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 全体 | デスクトップ | スマートフォン |
1 | 80.50%(+2.01pt) | 74.19%(-0.02pt) | 85.56%(+3.02pt) | |
2 | Yahoo! | 9.18%(-2.21pt) | 6.21%(-1.30pt) | 11.47%(-3.48pt) |
3 | Bing | 8.23%(-0.38pt) | 17.79%(+1.11pt) | 0.68%(-0.41pt) |
4 | YANDEX | 0.60%(+0.18pt) | 0.58%(+0.05pt) | 0.62%(+0.30%) |
5 | CocCoc | 0.58%(+0.32pt) | 0.26%(+0.14pt) | 0.80%(+0.42pt) |
出典:https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/japan
SEO(検索エンジン最適化)は、Googleの検索アルゴリズムの変化とともに大きく変遷してきました。Googleは、ユーザーにとって最も有益な情報を提供することを目指し、日々アルゴリズムの更新を重ねています。
以下に、Googleの主要なアルゴリズムのアップデートの背景と、それに伴って変化してきたSEOの手法を振り返りながら、各アップデートの狙いや、それがもたらした影響を整理していきます。

インターネットが急速に発展し、数多の検索エンジンが誕生していた1990年後半。この時代の検索エンジンのアルゴリズムは非常に単純であり、主に「キーワードの使用回数」や「文字数」「メタタグ」などの情報を基に評価をしていました。このようなアルゴリズムの裏を突いた隠しテキスト※などの手法が流行していたのもこの頃です。
※隠しテキスト…人間の目には見えないように白背景に白文字などでテキストを隠して、全く関係のないコンテンツを上位表示させる手法
そうした状況の中で登場したのがGoogleです。
Googleは、当時の主流だったYahoo!(ディレクトリ型検索※)とは異なり、ロボット型のクローラーによってWeb全体を巡回し、リンク構造をもとにページの重要性を判断する「PageRank」アルゴリズムを導入しました。PageRankとは、簡単に言えば「重要なWebページはたくさんのページからリンクされる」という考えのもと、Webページ間のリンク構造を解析してページの重要度を評価する仕組みです。
※ディレクトリ型検索…ユーザーが自分のWebサイトを検索エンジンに登録する際に、担当者が手動でサイトをカテゴリに分類し、検索結果に表示されるようにする方式です。
これにより、インターネット上の膨大なページの中からよりユーザーの検索意図に合致した結果を返せる点が評価され、Googleは急速に支持を集めていきます。
ただし、この時点では依然としてキーワード詰め込みや隠しテキストといった“原始的なSEO”も通用していたことは否めません。Googleが他の検索エンジンと一線を画していたのは、そうした状況の中でも「リンク評価」や「ページ全体の構造」に注目し、より“ユーザーのためになるサイト”を上位表示させる志向を持っていたという点にあります。
Googleの登場は、SEOというゲームのルールそのものに大きな変化をもたらしていくことになるのです。

2010年、Google社は大きな打ち手を出します。かつてのライバルだったYahoo社と提携し、「Yahoo!検索のアルゴリズムにGoogle検索のアルゴリズムを採用する」と発表したのです。
それまでYahoo!検索は、独自の検索アルゴリズム(YST: Yahoo! Search Technology)を採用していましたが、これにより検索エンジン市場は、実質的にGoogleの影響下に置かれることになります。
Googleのアルゴリズムが検索の基準となり、SEO業界は新たな局面を迎えることになりました。
Googleのアルゴリズムは精度が高く、これまで過剰なSEOをおこなっていた一部の業者たちは、その方法が効かなくなっていることを実感し始めます。小手先の裏技ではどうにもならない時代が、ゆっくりと、でも確実に始まりつつあったのです。

検索エンジンがYahoo!のような人力登録型から、Googleのクローラーによるロボット型へと主流が移る中で、Googleは検索品質を守るために隠しテキストやキーワードの詰め込みといった“過剰なSEO”を徐々に排除する方向にアルゴリズムを進化させていきました。
その流れの中で、2011年、GoogleはSEO業界にさらなる大きな波紋を呼ぶアップデートを実施します。その名も「パンダアップデート」です。英語圏で先行して導入されたこのアップデートは、低品質なコンテンツを排除するための強力な一手でした。
対象となったのは、キーワードを無理に詰め込んだだけの中身の薄いページや、他サイトをコピーしたようなコンテンツ、大量の低品質記事を機械的に量産する「コンテンツファーム」などです。これらのサイトは軒並み検索順位を大きく落とし、逆にオリジナリティのあるコンテンツなど、ユーザーのニーズに沿った価値のあるコンテンツが相対的に上昇します。
また、サイト内に低品質なページが多く存在していると、サイト全体の評価に悪影響が及ぶようになり、SEOの考え方そのものに大きな転換が迫られることになります。SEO業界はこの変化に対応せざるを得なくなり、「量より質」のコンテンツ制作へと大きく舵を切っていきました。SEOの流れが「ユーザー目線のコンテンツ重視」へと大きくシフトしていったのです。
なお、日本にパンダアップデートが展開されたのは2012年7月です。導入後も定期的に更新が行われ、質の低いコンテンツや大量生産された中身の薄い記事を抱えるサイトへの評価はさらに厳しくなりました。現在、パンダアップデートのアルゴリズムはGoogleのコアアルゴリズムに統合されています。

Googleは、パンダアップデートに引き続き、検索結果に対する考え方を大きく変えるアップデートを導入しました。それが「ペンギンアップデート」です。当時のSEOでは、PageRankがリンクの数に大きく依存していることが広く知られており、「リンクを増やせば順位が上がる」という単純なロジックが成り立っていました。
これにより、リンクファームと呼ばれるネットワークを構築し、自作自演のリンクで検索順位を押し上げる“リンク操作”がSEOの主流手法のひとつになっていたのです。もちろん、当時の市場ニーズや競争環境のなかでは、それも一つの合理的な選択でした。
しかしGoogleは、「量より質」を求める方向へと大きく舵を切ります。ペンギンアップデートでは、次のような“人為的で不自然なリンク”に対して、評価の見直しやペナルティを科すようになりました。
これにより、SEO業界におけるリンク戦略の常識が大きく変化していきます。それまで主流だった“数を確保する”戦略は通用しなくなり、結果的に、ナチュラルリンク、すなわち「ユーザーや第三者が価値を感じて自主的に設置するリンク」こそが、評価される軸へと移行していくことになります。
ペンギンアップデートは、Googleが「リンクもコンテンツと同様、ユーザー本位であるべきだ」と打ち出した象徴的なタイミングでした。
2012年、Googleはもう一つ、大きな転換期となるアップデートである「ベニスアップデート」を実施します。日本の検索結果にこのアップデートの影響が現れ始めたのは、英語圏よりも1年以上遅れてからでしたが、アルゴリズム自体は2012年に公表されました。
パンダアップデートがコンテンツの質にフォーカスしたものであったのに対し、ベニスアップデートは「誰に対して、どの検索結果を返すか」という“検索の文脈”に踏み込んだアルゴリズムでした。検索結果にローカル性(地域性)や、ユーザーの位置情報・検索履歴といったコンテキストを取り入れることで、よりユーザーにとって適した結果を表示しようとする方向に進んでいったのです。
特に初期段階では、ユーザーの所在地に基づくローカライズが中心でした。たとえば「整体」や「カフェ」といった検索ワードに対して、全国共通の情報ではなく、ユーザーがいる地域に関連した情報を優先的に表示するようになります。
これは、現在では当たり前となった「検索結果の個別最適化(パーソナライズ)」の原型であり、Googleが検索エンジンを単なる情報の羅列からユーザーに合わせたナビゲーションツールへと進化させていくうえで、非常に重要な一歩だったといえるでしょう。
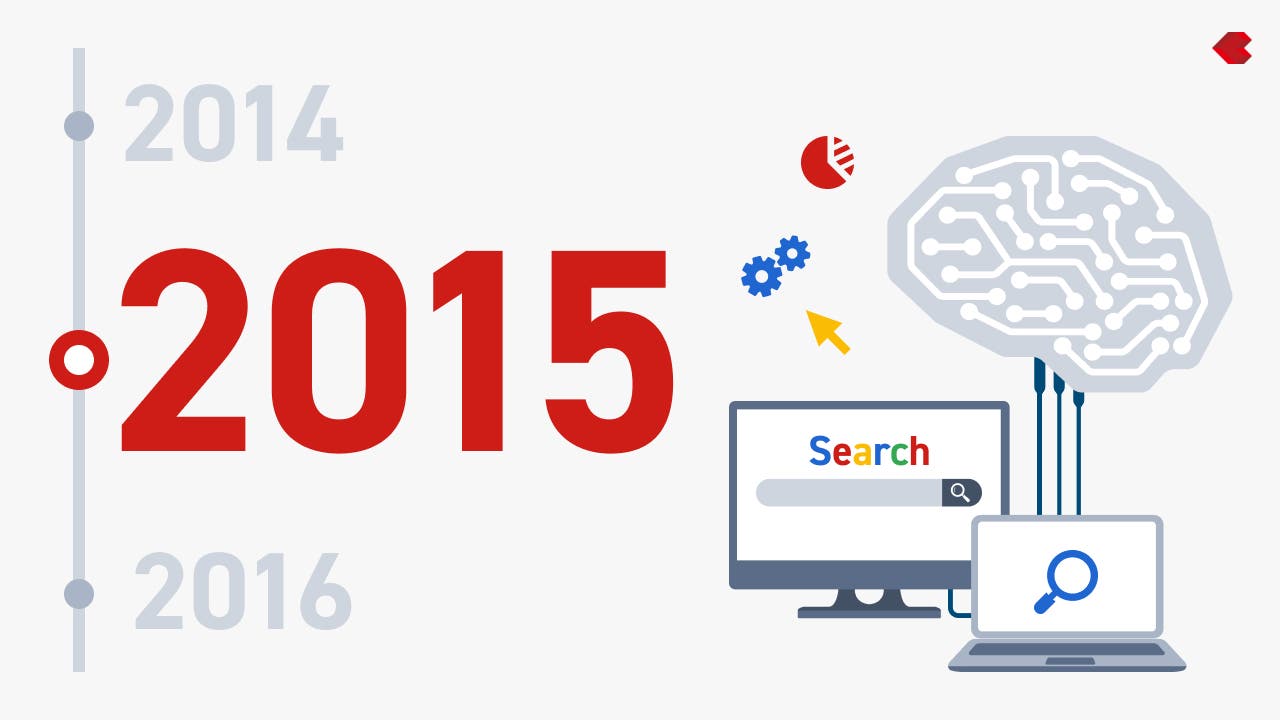
2015年、SEO業界にとって大きな転換期となる出来事がありました。Googleが機械学習を活用したアルゴリズム「RankBrain(ランクブレイン)」を検索順位決定に組み込んだのです。
このRankBrainの最大の特徴は、従来の「リンク」や「キーワードの一致」といった単純なルールベースの処理ではなく、過去の検索データから学習し、文脈や意味を解釈できるようになった点にあります。その結果、たとえば、「東京の美味しいディナー」と「東京で人気のディナー」というような表現の違いも、RankBrainは同じような検索意図として理解し、適切な検索結果を返せるようになりました。
従来のアルゴリズムでは捉えきれなかった複雑なクエリに対しても、より適切な検索結果が表示されるようになったことで、単にキーワードを盛り込むだけでなく、ユーザーが本当に求めている情報に焦点を当てることが求められるようになります。
RankBrainの導入により、SEOはアルゴリズムを「攻略」するのではなく、ユーザーの求める価値あるコンテンツを継続的に提供するという「本質」を重視する傾向が強まっていったのです。

この時期には、Googleの度重なるアルゴリズムのアップデートによって、検索結果の信頼性を一段と強化する方向へと舵を切っていきました。特に影響を受けたのは、個人のアフィリエイターを中心としたサイト群です。
特に、医療や健康ジャンルなどを含む「YMYL(Your Money or Your Life)」領域では、検索上位に誤情報や出典不明のアフィリエイトコンテンツが多く掲載されており、実際に社会的なトラブルに発展するケースも出始めていました。
こうした背景から、信頼性が強く求められるようになり、大手メディアや信頼性の高いドメインが優遇される傾向が強まります。これに伴い、それまで検索上位を席巻していたアフィリエイトサイトの多くが一斉に順位を落とし、「アフィリエイター冬の時代」「個人メディアの終焉」などと語られるようになります。
一方で、これは「すべてが大手優遇になった」という話ではありません。
Googleのアルゴリズムは定期的なアップデートを繰り返す中で、ドメインの信頼性や権威性の評価基準が強まったり、逆にコンテンツの質が再び強く評価されたりと、変動を繰り返しています。つまり、単に大手というだけで常に有利とは限らず、「専門性・権威性・信頼性(E-A-T)」を満たし続ける努力が必要になったということです。

2018年3月、Googleは「モバイルファーストインデックス(MFI)」の適用を開始します。これは、検索インデックスの評価基準をこれまでのデスクトップ版ではなく、モバイル版のコンテンツを基準にするという大きな変更です。
導入の背景には、スマートフォンを利用した検索ユーザーが増加し、モバイル端末からの検索体験を重視する必要が出てきたことがあります。このモバイル重視の流れは、2014年に実施された「モバイルフレンドリーアップデート」から始まりました。この時点で、モバイルでの閲覧に最適化されていないページは順位が下がる可能性があるとされ、モバイル対応がSEOにおける明確な評価項目となっています。
2018年に実施されたMFIの導入により、検索順位を決定する際の情報源としてモバイル版のページが“主役”となります。つまり、モバイル版にしかないコンテンツしか評価されず、モバイル版が不完全であれば、そのまま検索順位に影響が出るようになったということです。
この方針転換を受けて、SEO担当者やWebサイト制作者の間では、モバイル対応は“選択肢”ではなく“前提”となりました。レスポンシブデザインは標準装備となり、モバイルユーザーの体験を起点にした情報設計・導線設計が求められるようになります。
なお、MFIの適用は一斉に行われたわけではなく、すべてのサイトへの適用完了が発表されたのは2020年3月でした。つまり、モバイルの重要性は2014年からじわじわと高まり、6年かけて完全な転換が完了したということです。

2018年7月、Googleはモバイル検索においてもページの表示速度を正式にランキング要因に組み込む「Speed Update」を導入しました。これ以前のGoogleは、PC検索ではページの表示速度をランキング評価に取り入れていましたが、モバイル検索では速度に対する評価が明確にはされていませんでした。
しかし、スマートフォンが普及したことで、多くのユーザーがモバイル端末から検索を行うようになります。その一方で、モバイル環境は回線速度が安定せず、表示が遅いサイトではユーザーの離脱率が高まる課題が生じていました。
この問題に対応するため、Googleはモバイル環境においてもページ表示速度をランキング要因としたのです。結果として、SEO対策においてはモバイル環境下での表示速度改善やユーザー体験(UX)への配慮が欠かせない要素となりました。
単にキーワードを埋め込むような施策やリンク操作ではなく、Googleが重視する「ユーザーの検索意図を満たす質の高いコンテンツ作成」と、「快適なユーザー体験を提供する技術的な改善」という本質的な方向にシフトしていったのです。

2019年10月、Googleは自然言語処理モデル「BERT」を導入しました。これは、検索クエリの文脈や語順をより深く理解することを可能にしたアルゴリズムです。
BERTは、単語単体ではなく前後の文脈を加味して検索意図を読み取るため、「これまでのキーワードマッチ型」から「意味理解型」への大きな転換点といえます。結果として、ユーザーの曖昧な検索や口語的なクエリに対しても、より的確な検索結果が返されるようになりました。
このアップデートにより、SEOにおいては「検索キーワードを狙って詰め込む」よりも、「自然な言葉でユーザーの課題を解決するコンテンツ」がますます重要になります。これまで以上に、検索エンジンではなく“人に向けて書かれた”コンテンツが評価される時代に入っていきました。

2021年、Googleは次世代の自然言語処理技術「MUM(Multitask Unified Model)」を発表しました。BERTの1,000倍ともいわれる処理能力を持ち、検索クエリの理解にとどまらず、複数の情報源を統合し、質問の“意味”だけでなく“背景や意図”を理解しようとする段階に入ったのです。
また、MUMは多言語対応や画像理解も可能で、「英語で得られた医学情報を日本語ユーザーに適切に提示する」といった応用も視野に入っています。これにより、SEOではコンテンツ単位の最適化だけでなく、検索意図を前提に情報をどう構造化するかがさらに重要になっていきました。
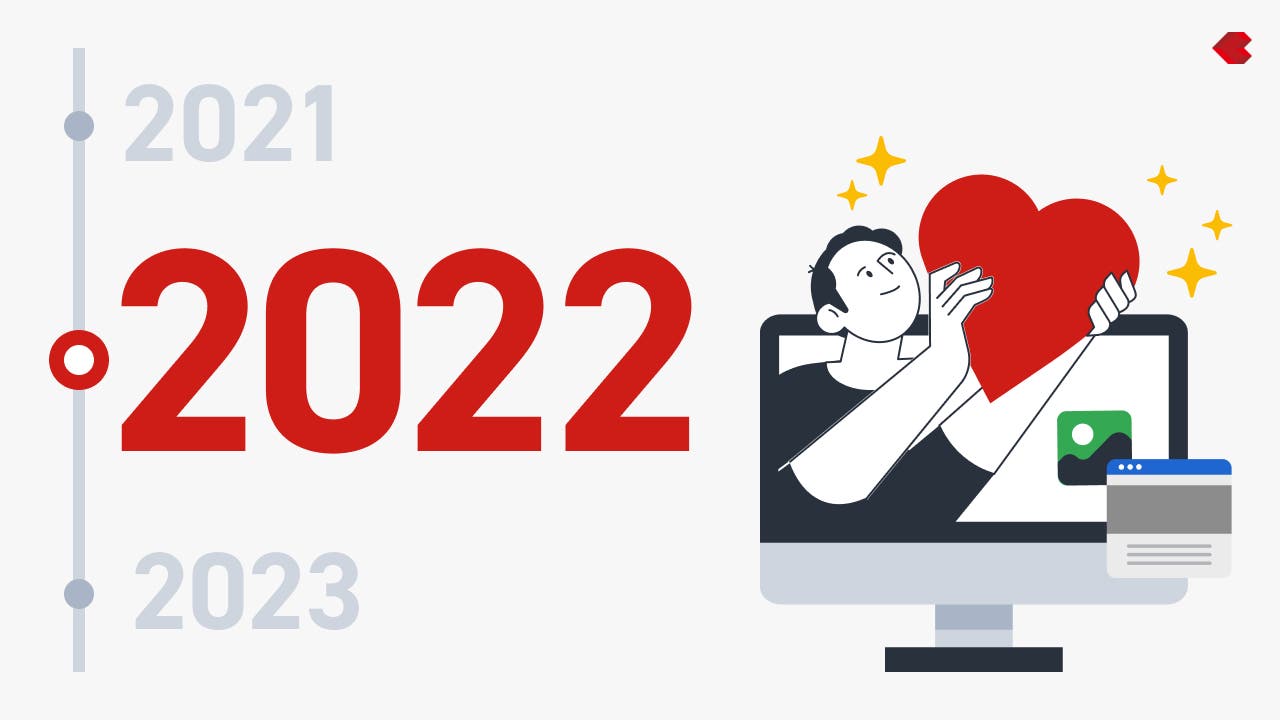
2022年8月、Googleは「Helpful Content Update(役に立つコンテンツアップデート)」を導入します。これは、「検索エンジンのために作られたコンテンツ」ではなく、「ユーザーのために作られたコンテンツ」を評価するという、Googleの基本姿勢をより強く押し出したアルゴリズムです。
以下のような特徴が見られたコンテンツは、順位を落とす可能性が高まりました。
実体験のない商品レビュー
他サイトの要約に過ぎない薄い記事
「このキーワードで上位を取りたい」という意図が透けて見える構成
このアップデートと歩調を合わせるように、Googleは「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」の概念に“経験(Experience)”を加えた「E-E-A-T」という評価フレームワークを打ち出します。これにより、検索評価において「実際に体験したことに基づいた情報」の重要性が一段と高まりました。特に、レビュー記事やノウハウ系コンテンツでは、実体験に基づいた独自の視点があるかどうかが強く問われるようになります。
SEOは、より「人間中心の設計」が求められるようになり、従来のテンプレート的なSEOライティングは根本的な再設計を迫られることになりました。

2023年、Googleは検索体験を根本から変える可能性を秘めた新たな取り組み「SGE(現:AI概要)」を発表しました。これは、生成AIを検索結果に統合し、ユーザーの問いに対してより包括的かつ自然な形で回答を提示するというものです。
この変化は、ユーザーの検索体験に大きな影響を及ぼしました。従来のように複数のリンクを比較して情報を集めるのではなく、検索結果ページ上で直接、要点を押さえた回答が得られるようになったのです。
さらに最近では、生成AIを中核に据えた“AI検索”サービスも登場し、検索の在り方そのものが急速に変化しています。従来の「探す検索」から、AIが答えを“生成して返す検索”へと主軸が移りつつあるのです。
こうした動きにより、SEOにおいても戦略の再考が求められるようになりました。たとえば、“AIが答えづらい問い”や“個人の体験・具体的な事例”など、より人間らしさが求められるコンテンツへのシフトが加速しています。SGEの登場、そしてAI検索の台頭は、SEOが「検索エンジン最適化」から「生成AIへの最適化」へと進化しつつあることを象徴する、歴史的な転換点だと言えるでしょう。
Googleの検索アルゴリズムは、これまで何度も大規模なアップデートを重ねてきました。その変遷を振り返ると、常に「検索エンジンのため」ではなく「ユーザーのため」のコンテンツが重視されてきたことがわかります。
低品質な記事や過剰なSEO施策は評価されにくくなり、代わりにユーザーの疑問や悩みを的確に解決する、わかりやすく信頼性のある情報が求められるようになりました。
そして現在は、AI概要に代表されるように、検索結果そのものが回答機能へと変化しつつあります。こうした変化の根底にあるのは一貫して、「ユーザーが本当に求めている情報に、迷わずたどり着けるようにすること」。それこそが、Googleの追求してきた本質であり、今後のSEOにおいても変わらず軸に据えるべき価値観といえるでしょう。