
【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2026.01.05
更新日:2025.08.22
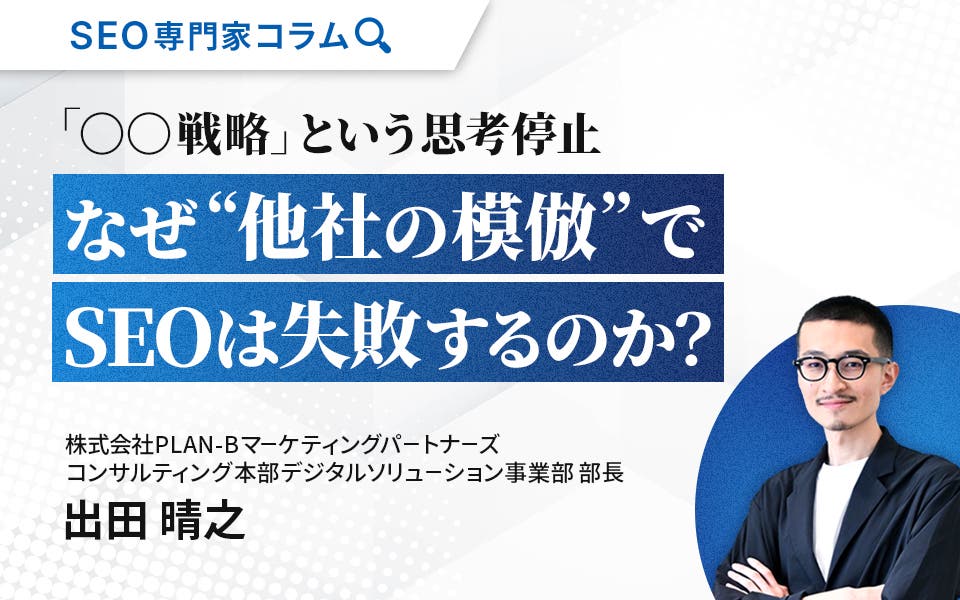
「これからのSEO戦略の王道は、トピッククラスター戦略だ」
「YMYLの分野で勝つには、とにかく権威性の構築が大切だ」
あなたの職場にも、「この戦略さえやればSEOはうまくいく」という空気はありませんか?
ブランドの知名度、専門家による監修体制、長年の運営実績など——これらの土台が異なれば、同じ戦略を模倣しても成果は得られません。むしろ、成果につながらない施策を積み重ねるばかりで、時間も資源も失われていきます。
この記事では、流行の戦略をそのまま採用するのではなく、自社にとって唯一無二の勝ち筋を定義するためのSEO戦略についてお伝えします。小手先のテクニック論ではなく、持続的な成果を生むための指針としてお役立てください。
他社の成功事例は魅力的に映りますが、その表面だけを真似るのは危険です。背景や条件を見極めないまま飛びつけば、気づかぬうちに失敗への道を歩むことになりかねません。
その背後には失敗へと導く落とし穴が潜んでいます。
各企業で成功事例として挙げられている戦略は、事業の状況や目的といった「コンテキスト(文脈)」があってこそ機能するものです。
たとえば、BtoCメディアでは、膨大な関連記事でユーザーの認知を獲得し、その一部をコンバージョンに繋げる「トピッククラスター戦略」が有効なことがあります。しかしこれを、リード獲得単価が極めて重要であるSaaS事業でそのまま適用すればどうなるでしょうか。商談につながらないような情報収集層のアクセスばかりが増え、トラフィックは伸びても事業は成長しない、という状況に陥りかねません。
さらに、AI Overviewsによって検索体験が変化している今、かつてのGoogle検索結果ページのような青色のタイトルリンクが10件ずらっと並んでいる状態(いわゆる”10 blue links”=10本の青いリンク)の中で「とにかく1位を狙う」という発想のままでいるのも、同じくコンテキストを欠いた対応といえます。
ある戦略がうまく機能するためには、それを支える「前提条件」が存在します。たとえば、YMYL分野で検索上位を取るには、多くの場合、医師や弁護士といった専門家による監修体制や、長年積み重ねたドメインの権威性が不可欠です。
仮にこうした前提条件が揃っていないスタートアップ企業が同じやり方を真似してもほとんど成果は出ず、無謀に等しい戦略といえます。
また、限られた人員や予算しかない中小企業が、大企業のように大量で網羅的なコンテンツ戦略を真似すると、結果として質の低い記事ばかりが増え、サイト全体の評価を下げる要因になりかねません。
最も深刻なのは、目的と手段の倒錯、つまり目的と手段が入れ替わってしまうことです。
たとえば「トピッククラスターを完成させること」や「目標キーワードで1位を取ること」といったものは、本来「事業を成長させる(売上・利益を増やす)」という目的を達成するための手段の一つでしかありません。
ところが、その手段の実行に固執しすぎることで、「なぜそれをやるのか」という本質的な問いが置き去りになります。結果として、本来目指すべき最終目標(KGI)を見失い、組織は時間も労力も消耗しながら、違う方向へ進んでしまう危険があるのです。
では、この罠からどう抜け出せばよいのでしょうか。答えは、「〇〇戦略」とは名ばかりの、単なる流行の“戦術”に振り回されるのではなく、自社だけのSEO戦略を明確にすることです。
この軸は、次の5つの問いに具体的に答えることで見えてきます。
多くのSEO戦略は「何をやるか(To Do)」に重点を置きますが、それだけでは不十分です。「何をやらないか(Not To Do)」を明確にすることで、戦略の輪郭はより鮮明になります。
SEOの本質は、限られたリソース(人的・時間的コスト)を集中させることです。そして集中とは、同時にそれ以外を「捨てる」ことでもあります。この「選択と集中」という決断にこそ、企業の意思と戦略性が表れるのです。
上記で上げた5つの質問について、実際に考えてみましょう。
問1.存在意義:我々のメディアは、ユーザーにとって「なぜ」存在するのか?
競合メディアではなく自社メディアを選んでもらうための理由を明確にします。提供価値が単なる情報提供なのか、それとも独自の視点や一次情報なのか、そして検索エンジンの先にいる“人”のどんな課題を解決しているのかまで掘り下げることで、メディアの存在意義が揺るぎないものになります。
具体的な問い)
問2.未来像:3年後、検索エンジンとユーザーからどう認識されたいか?
たとえば、「専門家向けに、深い情報を発信するサイト」「初心者向けに、わかりやすい情報を発信するサイト」として認識されたいのかなど、未来の理想像を描くことで、現在の施策に一貫性と方向性が生まれます。
具体的な問い)
“○○といえばこのサイト”と真っ先に思い出されたいテーマは何か?
どんな場面・検索意図のときにユーザーに想起されたいのか?
問3.主戦場:我々が本当に戦うべきキーワード群はどこか?
競合がひしめくようなビッグキーワードに貴重なリソースを投下していないか考えてみましょう。もちろんビックキーワードを狙うことは悪でありません。しかし、よりコンバージョンに近く、競合が手薄な「儲かるミドル~スモールキーワード」に主戦場を変更できないか、一度検討する価値はあります。
また、「戦うべきは本当に検索結果だけなのか」という点も、改めて考えてみてください。SNSやコミュニティなども含め、顧客の情報収集ジャーニー全体を主戦場として捉え直すことも重要です。
具体的な問い)
現在注力しているキーワード群の中で、順位獲得に最もコストがかかっているのはどのキーワードか?
問4.非対称な優位性:競合サイトが模倣できない、我々だけの武器は何か?
「競合が真似できない、自社だけの強み」を考えてみましょう。ここでいう「強み」とは、単なるスキルやノウハウではなく、他社が短期間では手に入れられない独自資源のことを指します。
例えば、それは社内にいるプロダクト開発者や営業担当者が持つ深い専門知識かもしれません。あるいは、自社だけが持つ独自の調査データや、豊富な導入事例といった一次情報かもしれません。さらに、長年かけて育ててきた、熱量の高いユーザーコミュニティという場合もあります。
こうした「唯一無二の武器」を活かせないSEO戦略は、どれだけ理論的に正しく見えても、本質的な価値がありません。
具体的な問い)
自社だけが持っている情報やデータは何か?(例:独自調査、顧客利用データ、業界統計など)
社内の誰が、他社にない専門的な知識や経験を持っているか?
過去のプロジェクトや導入事例で、他社が簡単に再現できない成功パターンはあるか?
問5.戦略的棄却:勝利のために「やらないこと」は何か?
これが最も重要で、最も困難な問いです。例えば、
このような問いに対する答えが、あなたの会社だけの「SEO戦略」の判断基準となります。今後、新たな「〇〇戦略」が現れた時、あなたはこの判断基準に照らし合わせるだけで十分です。「その戦術は、自社の未来像に合致するか?」「自社の主戦場で有効なのか?」「自社の武器を活かせるか?」——もし答えがNoであれば、その選択肢は迷いなく捨てましょう。
私たちは、日々あふれる情報の中で暮らしています。SEOやLLMに関する新しい流行語は次々と現れ、つい飛びつきたくなる“甘い誘惑”のように感じられます。ですが、本当の事業成長は、そうした安易な真似事の先にはありません。
ここでお伝えした「SEOの基本方針づくり」は、戦術の実行にとどまらず、事業全体の方向性を設計する役割を担えるようになるための考え方です。
まずは一例として、「狙わないキーワードリスト」を作ることから始めてもよいでしょう。「事業に貢献しないユーザー層は誰か」「自社の強みを活かせないテーマは何か」。こうした“やらないこと”を決めるプロセスを通じて、自社が進むべき方向や投資すべき領域が見えてきます。
戦略とは、一度作って終わりの静的な計画ではありません。検索エンジンと、その先にいる人と向き合いながら、常に問い続け、仮説を試し、磨き上げ続ける動きそのものです。考えることをやめず、問いを持ち続けてください。それこそが、不確実な検索の未来を生き抜くための、唯一にして最強の戦略です。
■株式会社PLAN-Bについて
SEO対策やインターネット広告運用などデジタルマーケティング全般を支援しています。マーケティングパートナーとして、お客様の課題や目標に合わせた最適な施策をご提案し、「ビジネスの拡大」に貢献します。
■SEOサービスについて
①SEOコンサルティング
SEO事業歴18年以上、SEOコンサルティングサービス継続率95.3%※の実績に基づき、単なるSEO会社ではなく、SEOに強いマーケティングカンパニーとして、お客様の事業貢献に向き合います。
②SEOツール「SEARCH WRITE」
「SEARCH WRITE」は、知識を問わず使いやすいSEOツールです。SEOで必要な分析から施策実行・成果振り返りまでが簡単に行える設計になっています。
■その他
関連するサービスとしてWebサイト制作や記事制作、CROコンサルティング(CV改善サービス)なども承っております。また、当メディア「PINTO!」では、SEO最新情報やSEO専門家コラムも発信中。ぜひ、SEO情報の収集にお役立てください。
※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象
※集計期間(2024/01~2024/12)中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様(当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上)が対象