
【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2026.01.05
更新日:2025.08.06
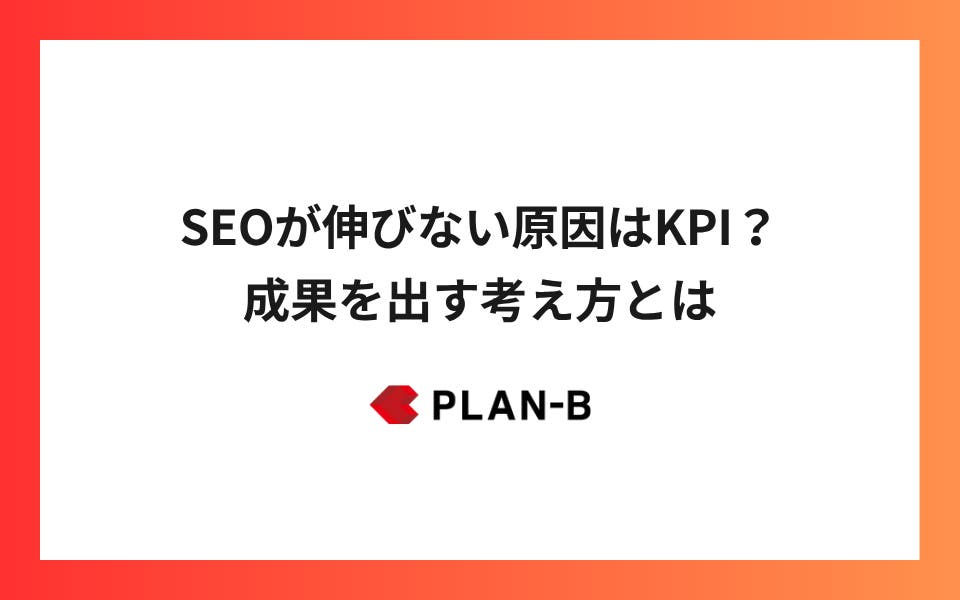
「SEOに取り組んでいるけど、問い合わせにつながらない」
「記事はたくさん書いているのに、なかなか効果を実感できない」
そんな状態に陥っていませんか?
それはもしかすると、KPI設計のミスが原因かもしれません。
【この記事でわかること】
SEO施策が売上や問い合わせにつながらない理由
成果につなげるためのKPI設計の基本と落とし穴
フェーズごとに変わるKPIと、その設定の考え方
KPIをノルマにしないためのアドバイス
今回は、PLAN-Bのプロダクトマーケティングマネージャー・松本に、「SEO施策が成果につながらない理由」や「正しいKPI設計」について話を聞きました。
本記事ではその内容をわかりやすくまとめています。SEOに取り組み始めたばかりの方も、成果が出ずに悩んでいる方も、ぜひご一読ください。
PINTO!編集部:本日はSEOにおけるKPI設計の重要性についてお伺いしたいと思います。
とはいえその前に、そもそもSEOを始めたばかりの企業が最初に悩みがちなことってどんなことでしょうか?KPI以前の段階でつまずいているケースも多いのではないかと思います。
松本:そうですね。SEOって、結構専門的な知識が必要そうなイメージがあってとっつきにくいと思われていることが多くあります。そういった背景もあって「まず何から始めたらいいか分からない」という声はよく聞きます。初めてSEOを任された担当者にとっては、成果を出すための取っ掛かりが見えづらく、どこから手を付けていいかがわからないっていうのがかなり多いと思いますね。
PINTO!編集部:一生懸命SEOに取り組んでいるのに、なかなか成果が出ないという企業も多いと思います。そういった企業に共通する点はありますか?
松本:一言で言うと、「正しいやり方でSEO対策ができていない」ケースが多いです。自社ではやっているつもりでも、プロの目から見ると「ズレたやり方になっている」という状態です。
PINTO!編集部:「やっているつもり」と「できている」の間には大きな隔たりがあるんですね。
松本:そうですね。自己流で進めてみているが、うまくいっていない状態になっているケースは本当に多いですね。
断片的な知識だけ持っているが、全体像が見えていないことでズレを生んでいるみたいなケースです。
たとえば、「検索ボリュームが大きいキーワードから対策すべき」という情報でキーワード選定を行った結果、サイト全体として「どんな層にアプローチすべきか?」「競合の強さ、売り上げとの近さを加味したか?」といった本来必要な軸を欠いたキーワード戦略になってしまう、といったケースです。
こういった場合だと、偶然流入を増やすことができても、そこから売り上げに結びつかないという状態になってしまうのです。
PINTO!編集部:たしかに、「流入は増えているのに売り上げは変わらない」という話はよく聞きます。SEOを売上に繋げるためには、取り組む前にあらかじめ戦略、それに紐づく目標やKPIを整理しておくことなどの準備が大切だと感じますが、そうした準備ができている企業は多いのでしょうか?
松本:残念ながら、あまり多くはないと思います。「SEOをやらなければいけない」という漠然とした危機感から、「とりあえず始めてみる」というケースが多いのではないでしょうか。
PINTO!編集部:そもそも、SEOにおいてKPI設計はどれほど重要なのでしょうか?
松本:KPI設計は、SEOにおいて非常に重要です。SEOに限らないですが、KPIは、組織の行動を方向付ける羅針盤のようなものです。KPIを定めることで何を達成すべきか明確になり、SEO担当者はそのKPI達成に向かって努力します。指針であり行動原理を決めるものですから重要です。
特にSEOでは、計測できる数値が多く何をKPIにするかなど迷いがちなので、そこが注意ですね。
PINTO!編集部:なるほど。目標が明確になることで、担当者のモチベーションも高まりますよね。
PINTO!編集部:KPIを設計する前に、決めておくべきことはありますか?
松本:「今何に注力すべきか」という戦略を決めておくことが大切です。
SEO施策を進める中でも、たとえば「コンテンツの質を高めるべきタイミング」なのか、「まずは記事数を揃えて認知を広げる段階」なのか、「既存記事のリライトでCVを狙う段階」なのかによって、置くべきKPIは変わります。 こうした注力ポイントが曖昧なままだと、KPIも「数字を並べただけの目標」になりかねません。KPIは単なる数字ではなく、「今何を達成したいのか」を実現するための中間指標です。
だから、最初に「自社のSEOで今もっとも注力すべきこと」を見極め、それをKPIに落とし込むことが重要だと考えています。
PINTO!編集部:「何をKPIに置くか」を間違えてしまうケースも多そうです。SEOの現場で、KPI設計の「よくある間違い」にはどんなパターンがありますか?
松本:よくあるのは、SEOの運用フェーズに対して置くべきKPIが合っていないケースです。例えば、メディアを立ち上げたばかりなのに、いきなりコンバージョン数をKPIに設定したり、逆に、メディアが成熟してきているのに、記事本数をKPIに設定したりするケースです。つまりは、注力する事象がずれているというケースですね。
PINTO!編集部:メディアの成長フェーズに合わせてKPIを変えていく必要があるんですね。
松本:そうです。常に「今、何をすべきか、逆何を捨てるべきか」という視点を持ってKPIを設定する必要があります。
PINTO!編集部:KPIを立てる順番のようなものはありますか?例えば、SEOの初期フェーズは記事本数、次にセッション数というイメージです。
松本:事業の方向性や業界によって異なりますが、記事メディア型のSEOであれば、次の3段階で設定できることが多いです。
PINTO!編集部:初期フェーズでは記事本数をKPIにすることが大事なんですね。でも、記事数を増やすことに注力すると質が下がってしまう不安もありそうですが、「質より量」で大丈夫なのでしょうか?
松本:初期段階に限れば、質を追い求めることにこだわりすぎるより記事数をある程度確保することが重要です。そもそも記事が一定数ないと、検索エンジンに「このサイトがどんなテーマを扱っているのか」を認識してもらえません。
まずは、記事数が一定あり、評価される記事が出てきたりすると、サイト全体の評価も上がり、記事ごとに上位を目指すための土台を作れるんです。
PINTO!編集部:SEOの初期段階では、まず検索エンジンにサイトを認識してもらうことが大切なんですね。
松本:そうです。初期は多少質が粗くても記事の量を増やす方が重要であることが多いです。ただし、数を追うことをずっと続けていては本来のゴールに届きません。
繰り返しになりますが、大事なのは、「今、何に注力すべきか」を決めた上で、それを達成するための指標をKPIとして設計することです。メディアのフェーズや事業目標によって、注力ポイントは変わっていきます。フェーズが進んだら、目的や注力すべきことを見直し、それに合わせてKPIも設計し直す必要があります。
KPIはノルマではなく、あくまで事業目標に向かうための手段として使うという意識が重要です。
PINTO!編集部:KPIを設定する際の注意点はありますか?
松本:KPI設定で注意すべきなのは、「そのKPIを追いかける中で、本来取るべき行動がきちんと取れる設計になっているかどうか」です。
KPIは、設定を間違えると逆効果になることがあります。たとえば、マーケティング部門で「リード獲得数」をKPIに設定した場合、KPIを達成することばかりに意識が向き、数を優先するあまりリードの質が下がってしまうという事態が起きます。これは、KPIを「どうすれば一番簡単に達成できるか」という抜け道を探すような行動(=ハック思考)が働いてしまうためです。KPIの置き方次第では、チームの行動が意図しない方向に進んでしまう可能性があるんです。
PINTO!編集部:KPIの設定によって、想定外の力学が働いてしまうリスクがあるんですね。どうすれば、そのリスクの発生を防ぐことができますか?
松本:元からハックされる前提でKPIを設計し、ハックされたとしても「本来注力すべき正しい行動」が取れるようにしておくことが重要です。たとえば、SEO立ち上げ期において、「記事本数」や「表示回数」など、試行の多さや露出の広がりにフォーカスしたKPIを設定しておけば、たとえハックされたとしても「記事を出してみる」「試してみる」という行動は止まりません。
KPIは「行動が歪まないか」ではなく、「歪んでも必要な行動が取れるか」という視点で設計する意識が重要なんです。
PINTO!編集部:現在SEOに取り組んでいる企業が、自社のKPI設計が正しいかどうかをチェックできる観点はありますか?
松本:「なぜ、そのKPIなのか?」を第三者に説明できるか、自問自答してみてください。そもそもKPIは、実現したいゴールに向けて今注力すべきことを明確にするためのものです。たとえば、「記事本数」をKPIに設定したなら、それはまずは検索エンジンにサイトを認識してもらう段階だからという明確な意図があるべきです。
戦略とKPIがちゃんと紐づいているかを確認することが、正しいKPI設計の第一歩になります。
それができれば、あとはハック思考を走らせたときに取る行動が、本来取ってほしい行動かどうかのチェックですね。
PINTO!編集部:KPI設計ができているつもりでも、運用段階でうまくいかなくなるのはどんなパターンが多いですか?
松本:典型的なのは、KPIをたくさん設定しすぎて結局、やるべきことの優先順位がついていないパターンです。見るべき指標が多すぎると、結局何に注力すればいいか分からなくなってしまいます。
例えば、「キーワードごとのクリック率」「直帰率」「被リンク数」「作成記事本数」「セッション数」など、あらゆる指標をKPIとして追っているというのは、どの数字を優先的に改善すべきか決まっていないことと同じです。
PINTO!編集部:全部を改善しようと思うと、結局一つも良くなっていないなど起こってしまいそうですね。KPIを絞り込むことが重要ですね。
松本:そうですね。チームを組んで複数人で複数のKPIを持つ場合もありますが、その場合はチーム全体で「何を目指しているのか」という戦略の共有は必要となります。
PINTO!編集部:SEOを始めるにあたって、最低限必要なリソースはどれくらいでしょうか?
松本:理想を言えば、初期段階ではSEOにフルコミットできる専任の担当者を1人は置くことをおすすめします。特に立ち上げ期は、キーワード設計・コンテンツ制作・テーマや構成の仮説検証などやるべきことが多く、片手間では対応が難しいのが実情です。
PINTO!編集部:やはり兼任では難しいのでしょうか?
松本:兼任でも進められるケースはあります。実際、SEARCH WRITEをご利用いただいているお客様の中には、兼任体制でうまく回している企業もあります。ただ、それが成り立つのは、「SEOの経験が豊富な担当者がすでに社内にいる」「過去にSEOを運用していた人が新たに入社した」などにより、以下の条件が整っていることが前提です。
「優先順位を適切に判断できる」とは、たとえば「今はまずドメイン評価を高めるために記事数を確保するフェーズ」「今は既存記事のリライトで流入改善を図るフェーズ」といったように、SEOの目的やフェーズに応じて何に注力すべきかを見極め、それに沿って工数配分を決められている状態を意味します。外部からのサポートありでも、こういった状態を作れているというのが第一歩です。
また、「実施作業とスケジュールが明確になっている」というのは、たとえば、キーワード調査・構成案作成・記事発注・レビュー・効果検証といった各工程をどの順で進めるかが整理されており、かつその作業を「誰が/いつ/どのくらいの頻度で対応するのか」まで具体的に決まっているような状態です。
具体的なオペレーションが見えているのといないのとでは、初動のスピードや周りを巻き込んで進められるかに大きな違いが出ます。
PINTO!編集部:兼任でも進められるのは、SEO経験がある担当者がいて、注力すべき施策と、実施する内容やスケジュールが明確になっている時なんですね。
ただ、SEO経験が豊富な担当者がいるケースは、少ないのではないでしょうか?
松本:そうですね、SEOの経験が豊富な担当者が最初から社内にいるケースは多くはありません。専任を置くのが難しい、SEOの経験がまだ浅いという場合は、外部の支援を活用するのも一つの有効な選択肢だと思います。
たとえばPLAN-Bの「戦略設計・施策代行プラン」では、各社のビジネスモデルやターゲットユーザーの行動を踏まえた戦略設計から、記事制作、効果検証までを一貫して支援します。
また、進捗状況や成果は自社開発のSEOツール「SEARCH WRITE」で常に可視化できる仕組みになっていて、施策の意図がブラックボックス化される心配もありません。単なる記事作成の外注先ではなく、「なぜこの施策をやるのか」をしっかり理解しながら伴走できるのが特徴です。
PINTO!編集部:リソースや経験が限られていても、SEOを立ち上げたいと考える企業に合わせたプランなんですね。
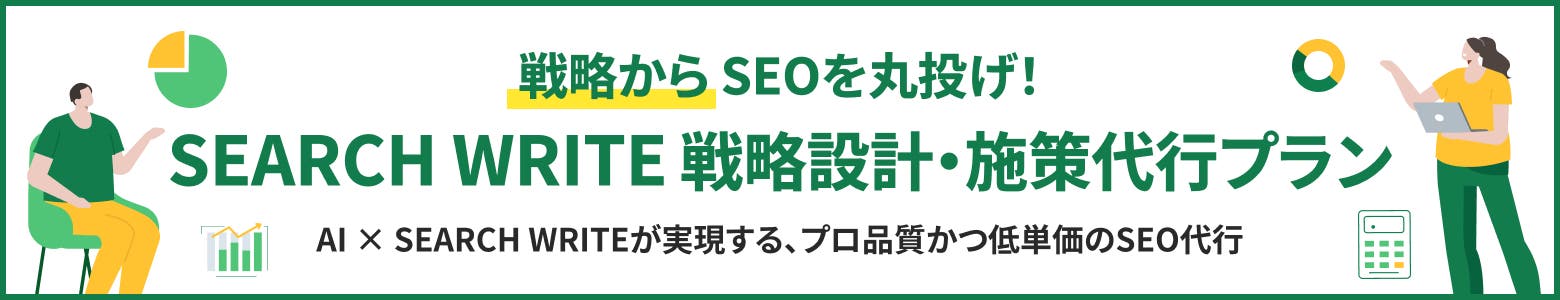
PINTO!編集部:SEO運用において、外注ではなくSEOツールを検討されるケースが多いと思いますが、ツールを導入するよりも外注を選んだ方がいい時とは、どんな時ですか?
松本:ツールを使いこなせない時です。他業務と兼任している担当者や、SEOの経験が浅い担当者の場合、ツールに使う時間を確保できなかったり、どのデータを見るべきかがわからず、十分に使いこなすことが難しい傾向があります。
PINTO!編集部:ツールを使いこなすには、ある程度SEOの知識や経験が必要なんですか?
松本:ツールの特性にもよりますが、知識や経験が必要な場合が多いです。また、ツールを活用するには、活用にリソースを割ける担当者が必要です。知識や経験が浅く、ツールを使いこなす時間がない企業は、外注した方が良い結果につながる可能性が高いです。
PINTO!編集部:将来的には内製化したいと考えている企業が、最初から外注に踏み切るメリットは何ですか?
松本:将来的な内製化を見据える場合でも、最初に外注を活用することで効率よくノウハウを吸収できることが大きなメリットです。外注先の担当者に目標設定の理由や施策の意図を確認したり、実際の施策に並走することで、SEOに必要な知識や判断軸を短期間で身につけることができます。一から独学で進めるよりも、正しい運用を見て学びながら経験を積めるため、内製化のスピードと精度が格段に高まります。
PINTO!編集部:最後に、SEOの進め方やKPIの立て方に迷っている企業に向けて、アドバイスをお願いします。
松本:「そのKPIは、注力するものと紐づいていますか?」という問いを常に自問自答してください。KPIは、戦略を達成するための指標です。何を実現したいのか、何に注力したいのかを明確にし、それをKPIに落とし込むことが重要です。
SEOの進め方で迷ったら、まずは「自社のSEOで、今もっとも注力すべきことは何か?」を考えてみてください。そして、その注力事項を達成するために最適なKPIは何か?という順番で考えることが重要です。
■記事内容まとめ
SEOの成果が出ない原因の多くは「KPI設計の不備」にあり、戦略と目的に即したKPIを設計することがSEO成功の鍵となる。
メディアのフェーズに応じて、記事本数→セッション数→コンバージョンと段階的にKPIを移行させていく設計が重要。
KPIはハックされるものだという前提を持ちつつ、たとえハックされても必要な行動や学びが止まらないように設計することが重要。