
【入門編】seoライティングの基本を7ステップで習得!
SEO対策
2023.10.30
2024.05.08
2024.05.13
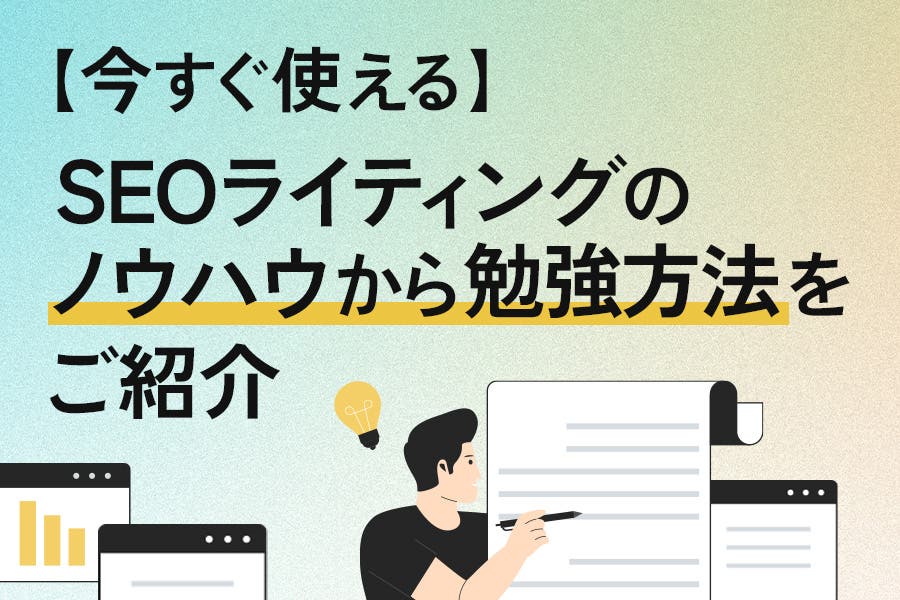
SEOライティングって聞いたことはあっても、具体的な方法や勉強方法ってあまりわからないですよね。
本記事では、今すぐ使えるSEOライティングのポイントから勉強方法までご紹介しています。
この機会にSEOライティングを身に着けたいとお考えの方は是非ご一読ください!
SEOライティングをするにあたって、そもそもSEOとは何かを改めてご紹介します。
SEOとは、Web集客の手法の一つであり、Googleなどの検索エンジンで自社のWebサイトをより上位表示させるための施策全般を指します。
今回はWebサイトの中でも、特に記事メディアを対象とした内容です。
SEO対策の中でもコンテンツの質をあげることに着目したコンテンツSEOにも、seoライティングは強い効果を発揮します。
「SEOライティング」とは、検索エンジンで上位表示させることを目的としたライティング手法のことです。
基本的にはSEOの知識を持ったうえで、記事のライティングをすることを指します。
一見、特殊なライティング手法のように感じますが、SEOライティングで一番重要なのは、ユーザーファーストなブログ・記事が書けているかどうかです。
SEOの勉強をすると、ユーザー目線とGoogle(コンピューター)目線の二つの視点で、いい記事がわかるようになるため、結果的に上位表示がしやすくなります。
ここでは、ユーザーファーストな記事を書くために必要なスキルをご紹介します。
情報収集力と読解力当たり前のことではありますが、基本的な文章力は必須のスキルです。今回は特にPINTO!編集部で気をつけているポイント4点をご紹介します。
記事作成の際には、記事を読むペルソナの設定や、検索意図を考える必要があります。網羅性や独自性を出すために、上位記事の調査や自社独自の情報を集めることも求められます。
いずれにしても正しく情報を集め、正しく情報を読み取り、そこから必要な情報を取捨選択する力が必要です。
SEOライティングはSEOの知識をもってライティングをすることです。
そもそもSEOとはどういうことなのかを知っていないとSEOライティングの質を高めることは難しいでしょう。
テクニカルな部分までは知らずとも、考え方や何が記事の評価につながるかは知っていることが重要になります。
まず、「何を」勉強するかですが、Webライティングの経験がある方は、SEOについて学びましょう。 Webライティング初心者であれば、WebライティングとSEOについて勉強する必要があります。
以下でそれぞれを学習する方法をご紹介いたします。
Webメディアの特徴は、気になるところだけ部分的に知ることができ、それでいてコンテンツの量が豊富なため、網羅的に知識を得られることにあります。
SEOの知識のほとんどをWebメディアで学ぶことができます。
PINTO!では「SEOを学ぶ」というコンテンツで最初に学ぶべき厳選された記事を読むことができます。必読レベル☆☆☆の記事を読んでいくだけでもSEOの考え方を理解することができますので、是非勉強にご活用ください。
以下は、SEOを学べるサイトをまとめた記事ですので是非ご活用ください。
Webライティングに関してもWebメディアで学ぶことができます。seoライティングのやり方について詳しく書いた記事と合わせてご活用ください。
ここではSEOの基礎を学べる本とWebライティングを学べる本を1冊ずつご紹介します。
引用:技術評論社
著者:土居健太郎
引用:マイナビBOOKS
著者:片桐 光知子
以下の記事ではオススメの本に関してまとめていますので、気になる方は是非ご覧ください。
セミナーでは学びたいトピックに絞って専門家から学ぶことができます。
seoライティングがテーマのセミナーを受けることもできますし、SEOの知識の足りてない部分だけ学ぶこともできます。
オンライン開催が多く、明確な疑問を持っている場合は直接質問ができるのもセミナーの強みです。
最近ではYouTubeでもSEOやライティングについて学ぶことができます。
個人的には、Webサイトや本と併用して視聴することをオススメします。Webサイトや本で核となる基盤を作り、YouTubeで個人的なポイントを聞きに行くイメージです。
動画や音声では、その話し手が大切だと思った部分に抑揚がつく傾向があります。上級者が思う現場レベルのポイントがわかるのが特徴です。
ここではオススメの動画を2つご紹介します。
ここまでインプット方法をご紹介しましたが、SEOライティングはインプットだけしていても上手くなりません。
SEOの知識とWebライティングの知識をつけながら、継続的なアウトプットの機会を設けることが重要です。
上記で紹介した勉強方法や本記事でのSEOライティングのポイントを確認しながら自身で記事を書いてみることをオススメします。
SEOを勉強すればすぐにSEOライティングができるかというとそういうわけではありません。今回は、レベル別に意識すべきポイントを紹介しますので、SEOの勉強を進めながら活用してみてください。
ユーザーは目次や導入文をみて、ほしい情報がないと判断したらすぐに記事から離れてしまいます。 目次だけを読んでも、この記事で何を知ることができるかわかる構成と文章を意識しましょう。
わかりやすい目次は、並列関係にあるものの粒度がそろっており、関連する情報が一つの見出し内に集まっています。
導入文には、ユーザーへの共感、課題の提起、そしてそれを解決できる記事であることを示すと良いでしょう。文章の意図がばれると歯がゆい感じがしますが、下図で本記事の導入文の意図をご紹介します。
上位表示されている競合ページをもとに、適切なテキストボリュームを決めます。しかし、競合ページのテキストボリュームはあくまで目安です。くれぐれも、テキストボリュームが足りていないから冗長で無駄な文章を増やす、などはしないようにしてください。
画像や図は視覚的な理解を促し、ユーザーが記事を読むハードルを下げることができます。
一方で、基本的にGoogleはテキストでWebページを評価しているため、画像ばかりになってしまうとGoogle観点ではあまりよくありません。
画像や動画が増えると、読み込み速度が遅くなり、ユーザビリティが損なわれるという可能性もあります。
理解しづらい内容の図解やイラストはオススメです。また、文章が長くなってしまった際に、内容をまとめた画像を挿入するのも良いでしょう。
文字数は全角27~32文字以内に収めるのがよいでしょう。最近では32字以内でもタイトルが見切れることがあるため、30文字に収める方が検索画面でタイトルが見切れる心配がありません。
また、思わずクリックしたくなるキャッチワードを設定することも重要です。
そもそも網羅性と独自性とは、ユーザーが必要としている情報を漏れなく提供することと、自社のみが持つ情報を提供することです。
具体的な内容を見ていきましょう。
まず、網羅性を担保するためには、上位ページを見てユーザーが必要としているかつ、自社サイトに足りていない項目を洗い出して取り入れましょう。
しかし、100%参考になるとは限らないため、トピックのみを参考にし、構成も含め中身はオリジナルにすることを推奨します。
これは落とし穴ですが、自社にない情報は書かないように注意しましょう。
独自性の出し方は、自社で行った調査結果などの掲載がオススメですが、いくつか具体策もありますので見ていきましょう。
書籍、インタビュー、海外サイトから引用すると他との差別化ができます。そもそも上位サイトが外部サイトを参照していないケースもあるため、競合があいまいにしている部分を、自社メディアでは情報ソースを明示することで独自性にすることができます。
自社で実施した実績、経験があれば具体的な数値で事例を紹介しましょう。自社事例は真の一次情報といえるので、独自性を出すには効果的です。
実際に挑戦した経験や、自身の主観もオンリーワンのコンテンツになります。ただし、主観的な意見・見解を話す際は、あくまで断定できないことを明記することに気を付けましょう。
特に、失敗談は、情報収集している人にとって非常に有用なコンテンツであるため、臆せず記載するとよいでしょう。
ユーザー目線に立ち、「上位サイトに書いてある内容はユーザーのニーズを本当に満たせているか」と自問し、新たな見出しを追加できないか考えてみましょう。 SEARCH WRITEなどのキーワードツールを使うことでユーザーの隠れたニーズを見つけ出すことができるかもしれません。
初心者向けの記事であれば、専門用語は使わない、解説をする、より詳しい記事へのリンクを設置するなど、ユーザーの疑問や悩みを先回りして解決することを心がけましょう。
テクニカルライティングとは、技術的な内容を読者にわかりやすく伝えるためのライティング手法です。
ここでは、PINTO!でのテクニカルライティングの方法を解説します。
主語と目的語/動詞が離れていると単語や句同士のつながりがわかりにくくなってしまいます。
主語と目的語/動詞が近いと、結論として誰が何をしているのかがすぐにわかるので、ユーザーに伝えたいメッセージが正しく伝わりやすくなります。
複雑な話になるほど重要になりますので、是非意識してみて下さい。
指示語ばかり使うと十分に内容が伝わらない可能性があります。特に、量や程度を示すときは数字を使って具体的に書くようにしましょう。
文章は可能な限り簡潔に、短くすることを意識しましょう。すべて書き終わった後に、削れる文章を探し、勇気をもって削除することをオススメします。(本記事でも1/3くらい削りました。)
せっかく書いたのにもったいないという気持ちも痛いほどわかりますが、何よりも重要なのはユーザーファーストであることです!
見出しも含め、箇条書きにするときは特に注意をしましょう。同じ見出しレベル内の並列関係が同じ粒度でそろっているかは要チェックです。
例えば、カレーに必要な具材を紹介します。というトピックがあったときに以下のリストに違和感を感じますでしょうか。
おそらく、水とルーは具材なのか?と思ったことでしょう。この二つは材料というくくり方をすれば違和感はありません。
今回はすぐに気づけたかもしれませんが、トピックの抽象度が高くなればなるほど分類自体が難しくなりますので、注意しましょう。
ここまでSEOライティングの方法から勉強の仕方までご紹介してきました。
効果的なSEOライティングをするためにはSEOの知識をもってユーザーファーストな記事を書くことが重要になります。
しかし、SEOライティングをしようと考えすぎていると、ユーザーのための記事であることを忘れてしまうことがあります。どこまでいってもユーザーのための記事であることが最優先であることは忘れないようにしてください。