
【2026年版】SEOとは?初心者向けに具体例や事例を紹介
SEO対策
最終更新日:2026.02.05
更新日:2025.07.07
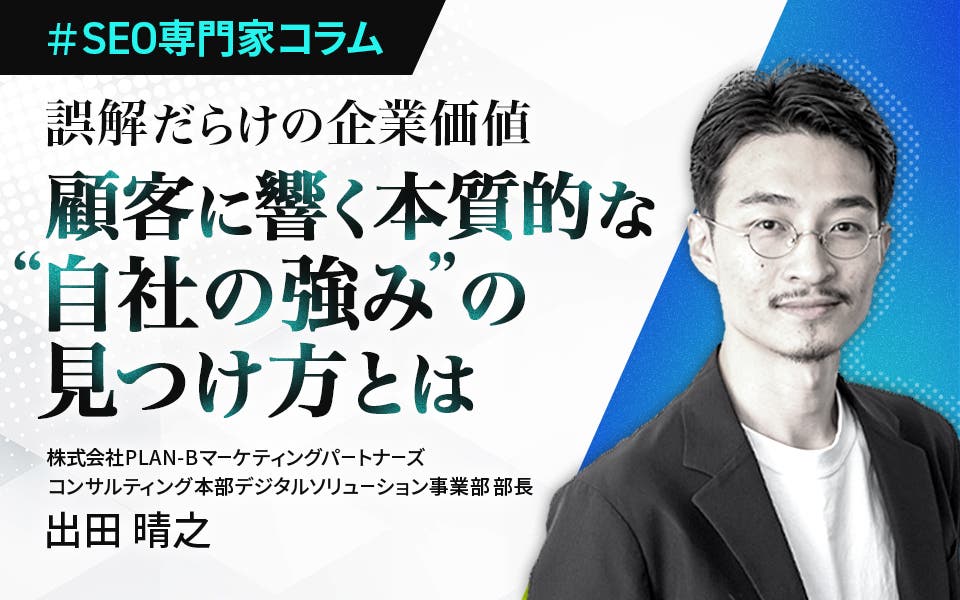
競争が激化する今日の市場環境において、企業が成長し続けるためには、「自社の強み」を正確に理解し、それを顧客に効果的に伝えることが不可欠です。しかし、多くの企業が「自社の強み」と捉えているものが、顧客にとっての価値と一致していないケースが散見されます。
たとえば、弊社がWebマーケティング支援を行っているクライアントさまの中にも、自社サイトのファーストビューに「自社の強み」ではなく、「自社の姿勢」や「業界カテゴリーの一般的な特徴」などを掲載してしまっているケースが見受けられます。
そこでこの記事では、企業が陥りがちな「自社の強み」に関する誤解を整理し、顧客に選ばれるための“真の強み”の捉え方、具体的な特定手法を解説します。
多くの企業が「自社の強み」を誤って認識しており、顧客から見て差別化につながらないポイントをアピールしてしまっているケースはとても多いです。このような状況では、競争優位を築けず、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。
ここでは、よくある間違った自社の強みについて解説します。
まず一つ目は、企業が「顧客のために頑張る」「丁寧な対応をする」といった企業努力や顧客対応の姿勢を強みとして誤認しているケースです。これらは顧客にとっては当たり前と思われていること多く、もはや業界の常識であり差別化には繋がりません。
つまり、選ばれる理由であるどころか、最低限の満たしていてほしい基準、いわば“スタートライン”に過ぎないのです。
そのような視点だけでアピールしてしまえば、顧客はその価値や他社との違いがわかりません。本当に必要なのは、「お客様が私たちを選ぶ理由は何か?」という問いに対して、競合と比べて明確に優れている“独自の価値”を見つけ、それを伝えることです。
努力や姿勢はもちろん大事ですが、それは「自社の強み」ではなく、事業を続けるうえでの“前提条件”と考えるべきでしょう。
「高品質」「豊富な実績」など、業界で共通する当たり前の要素を自社の強みとしてアピールしているケースも頻繁に見られます。しかし、これらはPoP(Point of Parity、同質化要因)と呼ばれ、その商品カテゴリーにおいて顧客から求められる最低限の要素です。
つまり、PoPも競争の土俵に立つための基準にすぎず、それ自体では選ばれる理由にはなりません。
例えばスマートフォンの通話機能やインターネット接続機能は、どの機種にも当然のように備わっています。それらの機能がないスマホはそもそも選ばれませんが、それだけで「この機種が欲しい」と感じる人はいません。これはまさにPoPの典型例です。
本当に選ばれるブランドになるためには、PoPを超えて「差別化要因=PoD(Point of Difference)」を明確に提示する必要があるのです。
続いては、競合他社を意識しすぎるあまり、独自性を欠いた「二番煎じ」になっているケースです。
例えば、他社の事例を見て表面的にそれをなぞるかたちで「業界最多の導入実績」や「スピード対応」などをアピールするなどです。そのような自社の強みは、どこかで見たことのあるような内容になりがちで、比較対象が増えるほど似たような選択肢のひとつに埋もれてしまいます。
かつてAppleの創業者スティーブ・ジョブズはこんな言葉を残しています。
「美しい女性を口説こうと思ったとき、ライバルがバラの花を10本贈ったら、君は15本贈るかい? そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に何を望んでいるのかを、見極めることが重要なんだ」
この言葉が示しているのは、他社が何をしているかではなく、“顧客が本当に求めているもの”を見極めることが何より大切だということです。他社と同じ価値軸で「うちのほうが上です」と競うだけでは、本質的な違いにはなりません。“他にはない視点”や“まだ誰も提供していない価値”が自社の強みであり、競合に振り回されるのではなく、まずはお客様の深いインサイトに向き合い、自社だけが提供できる価値を見つけ出すこと。それが選ばれるブランドへの第一歩となります。
企業が「自社の強みはこれだ」と自信を持っていたとしても、それが顧客にとって魅力的とは限りません。実際には、企業が自社の価値を客観的に捉えられておらず、過大評価してしまっているケースも少なくありません。結果として、顧客との認識にズレが生じ、「なぜ選ばれないのか分からない」という状況を生み出します。
こうしたズレの根本的な原因は、顧客の本音やニーズを深く理解できていないことにあります。たとえ企業側がどれだけ努力していても、その努力の方向性がズレていれば、望む成果にはつながりません。
自社の強みを知る手段として、アンケートやグループインタビューのような調査手法をとる方法もありますが、このような手法では顧客が「期待されている答え」を返してしまうこともあり、本音を引き出すのが難しくなります。また、理想像をもとに構築されたペルソナも、現実の顧客像とは乖離していることが多く、マーケティング施策が的を外してしまう原因になります。
その結果、企業は自分たちにとって都合の良い情報だけを信じてしまう「エコーチェンバー」状態に陥り、実際の市場の声と向き合えなくなってしまうのです。
また、「何でもできます」という万能型のアピールにも注意が必要です。一見すると強みに思えるかもしれませんが、何でも対応できるということは、裏を返せば「これが得意です」といった専門性が見えにくくなるリスクがあります。企業としての強みがぼやけてしまい、他社を圧倒する競争力を築くことが難しくなるのです。
そのようなオールラウンダー型の企業は、幅広い業務に対応できるというメリットがある一方で、これなら誰にも負けないという突出した強みが伝わりません。特に深い専門性が求められる領域においては、対応範囲が広くても「これが自分たちの得意分野です」と明確に打ち出せなければ、選ばれる理由が弱くなってしまいます。
本当に顧客から選ばれるための「自社の強み」とは、顧客視点から見て「なぜこの会社を選ぶのか」という問いに明確に答えられるものです。
ただし、単に自社が優れていると感じていることを強みと捉えても、それが顧客にとって意味のある価値でなければ選ばれる理由にはなりません。そこで重要になるのが、PoD(差別化要因)の考え方です。PoDとは、競合他社にはない自社だけが持つ独自の価値や魅力のことで、顧客が特定のブランドや商品を「選ぶ理由」となります。
なお、PoDをアピールする前提として、まずはPoP(同質化要因)をしっかり満たしておく必要があります。なぜならPoPは顧客から求められる最低限の要素であり、いわば競争のスタートラインといえるからです。顧客は、基本的な期待が満たされて初めて、その製品やサービスの持つ独自の価値を認識し、ブランドへの信頼を深めることができます。
PoPを満たした上でPoDを的確に打ち出すことで、顧客に選ばれるブランドとなり、ロイヤルティの獲得につながります。
| 項目 | PoP (同質化要素) | PoD (差別化要素) |
| 定義 | 競合と同等に求められる最低限の基準 | 競合にはない独自の価値 |
|---|---|---|
| 顧客の認識 | 「あって当然」 | 「選ぶ理由」 |
| マーケティング効果 | 差別化に繋がらない | 競争優位を確立 |
| 例 | スマートフォンの通話機能や通信機能 | ユニクロのヒートテック、Appleの直感的なUI |
💡QBハウスの事例
PoPとPoDの両立によって、業界内で明確なポジショニングを築いた好例として、QBハウスが挙げられます。QBハウスは、「10分・1200円・カット専門」というシンプルなモデルで注目を集めていますが、それが顧客に選ばれる理由となっているのは、まずPoP(同質化要因)をしっかりと満たしているからです。
たとえば、「一定の技術レベル」「安心して任せられるスタイリスト」「清潔で効率的な空間」といった、理美容サービスとして顧客が当然求める基本的な期待にきちんと応えており、これが信頼の土台となっています。
そのうえで、QBハウスは以下のような明確なPoDを構築しました。
こうしたPoDは、「フルサービスを前提とした理美容室」とは一線を画すものであり、「とにかく早く、安く、手軽に整えたい」という特定のニーズに的確に応えてています。PoPで顧客の基本的な期待をしっかりと満たしたうえで、PoDを強力に打ち出したことにより、QBハウスは「時短・低価格・ノンストレス」という軸で業界内の差別化に成功し、新たな市場を切り開くことができたのです。
PoDを特定する際に役立つのが、「どんな相手と競っているのか?」という競争の種類を4つの競争次元で考える方法です。以下に示した各競争次元において、自社がどう差別化できるかを考えることでPoDを見つけるヒントになります。
| 競争次元 | 説明 | 例(ビール市場) |
| ①ブランド競争 | 同じカテゴリーの商品・サービス同士の競争。 | アサヒスーパードライ vs. キリン一番搾り |
|---|---|---|
| ②産業競争 | 同一産業内の異なる製品形態の競争。 | ビール vs. 発泡酒 vs. 第3のビール |
| ③形態競争 | 顧客の同じニーズを満たす異なる製品形態間の競争。 | アルコール飲料全般(ビール、ワイン、ハイボール、チューハイなど) |
| ④一般競争 | 顧客の「時間・お金・関心」を奪い合うすべての選択肢 | 飲み物全般(水、ジュース、コーヒーなど)、あるいはレジャー、エンターテイメントなど |
参考:https://corp.neo-m.jp/column/marketing-research_101_category-entry-point-toha
競争次元が大きくなればなるほど市場も大きくなり、ターゲットの属性も広がり、便益も大きくなります。どの競争次元で差別化を図るべきかを戦略的に判断し、より上位の顧客課題を解決する視点を持つことが重要です。
「自社の強み」と聞くと、つい「うちのサービスは高性能です」「機能がたくさんあります」といった特徴を並べがちです。しかし、大切なのは、顧客がその特徴を通じて「どんな良いことが得られるか」というベネフィットを明確にすることにあります。つまり、製品のスペックだけでなく、それがあることで、どんな良いことがあるか、問題解決になるか、感情的な価値があるかを言葉にすることがポイントです。
顧客自身も気づいていない「本当の欲求(=インサイト)」まで深く理解することができれば、他社には真似できない本当の強みにつながります。
💡ベネフィットを明確にする具体的な方法
ベネフィットを明確にする方法はいくつかありますが、一例として「特徴や機能をベネフィットに言い換える」方法があります。例えば、「導入実績〇〇件」「 AI自動分析機能付き」といった特徴をもつBtoB向けの業務効率化ツールの場合、以下のような言い換えが可能です。
| 特徴 | ベネフィットへの言い換え |
| 導入実績〇件以上 | 同業他社が選んでいる安心感、導入失敗のリスクが低い |
|---|---|
| AI自動分析機能 | 分析作業の手間が減り、他の業務に集中できる |
| 専任担当がつく | 専門的なアドバイスがすぐにもらえ、迷わず進められる |
特徴に対して「だから何なのか?」と問い直すことで、上記のようなベネフィットが見えてきます。また、ユーザーインタビューなどで得た“生の言葉”をそのままベネフィット文に使うことも、効果的です。
どんなに魅力的な強みを伝えても、顧客に「それって本当?」と思われたままでは信頼につながりません。そこで大事なのが、根拠を添えることです。これをマーケティング用語では「RTB(Reason To Believe)」と呼びます。
たとえば、「業界No.1の実績があります」「お客様満足度90%」「第三者からの受賞歴があります」など、数字・事例・専門性などの証拠があることで、顧客がその価値を信頼し、購買行動を起こすための決定的な要素となります。
つまり、「私たちはこういう価値を提供します」と言うだけでなく、「なぜそれが信じられるのか」をセットで示すことが、強みとして成立させるうえで不可欠ということです。RTBを構成する要素には、以下のようなものがあります。
特定した自社の強みを、顧客に響く言葉で言語化することも大切です。「誰に・何を・どう伝えるか」を整理して、ターゲット顧客にとってわかりやすい言葉にすることで、はじめて伝わるようになります。
ページの印象は3秒以内に決まるとされ、直帰率や離脱率に大きな影響を与えるため、視覚的な設計も欠かせません。「何の会社か」「誰向けか」「何をしてほしいか」をぼやかさず、シンプルに、かつ自社らしさを込めて表現することが求められます。
ファーストビューで伝えるべき情報は、以下の3点です。
顧客中心の経営を実践するためには、まず社員一人ひとりが「顧客視点に立つことの大切さ」を理解し、それを日々の業務に取り入れることが重要です。そのためには、経営層から製品開発、マーケティング、営業、カスタマーサポートまで、すべての部門が連携しながら、顧客第一に考える社内文化を醸成していく必要があります。
その実現に向けた具体的な取り組み例としては、以下のようなものが挙げられます。
社内向けに「なぜ顧客視点が大事か」を定期的に伝える(社内報、キックオフ、朝礼など)。
部署横断のプロジェクトや定例会議で「顧客の声」や「ユーザー事例」を共有。
CRMやSFAなどのツールを導入・整備し、顧客とのやりとり、誰でも参照できる状態にする。
購入後の満足度調査や「推奨度」を聞く簡単なアンケートを実施する。
意思決定においては、数字による調査(たとえば顧客満足度のアンケートなど)だけでなく、実際の顧客行動や感情を深く理解するためのインタビューや観察といった、質的な調査も取り入れることが求められます。
ペルソナやカスタマージャーニーを作成する場合も、机上の理論にならないように、現実の顧客の声や行動に基づいて、定期的に見直していくことが大切です。NPS(ネットプロモータースコア)などの指標を活用し、顧客のロイヤルティを数値として把握し、改善策につなげていくことも効果的です。
市場や顧客のニーズは常に変化していくため、自社の強みが時代遅れになっていないか、あるいは競合が新たな魅力を打ち出していないかなどを定期的にモニタリングすることも必要です。こうした取り組みを確実に進めていくには、PDCAサイクル(計画・実行・確認・改善)を組織全体に根付かせ、常に顧客目線で物事を見直し、柔軟に戦略を更新していく姿勢が求められます。
場合によっては、ブランドの方向性を見直すこと(リポジショニング)も視野に入れる必要があるでしょう。
競争が激化する現代において、企業が持続的に選ばれ続けるためには、「自社が本当に提供できる価値」を顧客視点で見つめ直すことが必要不可欠です。
しかし多くの企業が“自社の強み”と思い込んでいることが、実は顧客にとっては当たり前の条件(PoP)であり、差別化になっていないケースは少なくありません。だからこそ、自社ならではの価値を明確にし、それが「誰にとって、どんな良いことにつながるのか」をわかりやすく伝える必要があります。
さらに、その価値が信頼できるものであることを、実績や証拠をもって裏づけることも重要です。企業の視点ではなく、常に顧客の視点から問い直すこと。それが、自社の強みを再定義し、真に選ばれるブランドになるための第一歩なのです。
■株式会社PLAN-Bについて
SEO対策やインターネット広告運用などデジタルマーケティング全般を支援しています。マーケティングパートナーとして、お客様の課題や目標に合わせた最適な施策をご提案し、「ビジネスの拡大」に貢献します。
■SEOサービスについて
①SEOコンサルティング
SEO事業歴18年以上、SEOコンサルティングサービス継続率95.3%※の実績に基づき、単なるSEO会社ではなく、SEOに強いマーケティングカンパニーとして、お客様の事業貢献に向き合います。
②SEOツール「SEARCH WRITE」
「SEARCH WRITE」は、知識を問わず使いやすいSEOツールです。SEOで必要な分析から施策実行・成果振り返りまでが簡単に行える設計になっています。
■その他
関連するサービスとしてWebサイト制作や記事制作、CROコンサルティング(CV改善サービス)なども承っております。また、当メディア「PINTO!」では、SEO最新情報やSEO専門家コラムも発信中。ぜひ、SEO情報の収集にお役立てください。
※弊社「SEOコンサルティングサービス」を1ヶ月を超える契約期間でご契約のお客様が対象
※集計期間(2024/01~2024/12)中に月額最大金額を20万円以上でご契約のお客様(当社お客様の87%は月額最大金額が20万円以上)が対象