
SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2025.07.15
更新日:2025.06.25
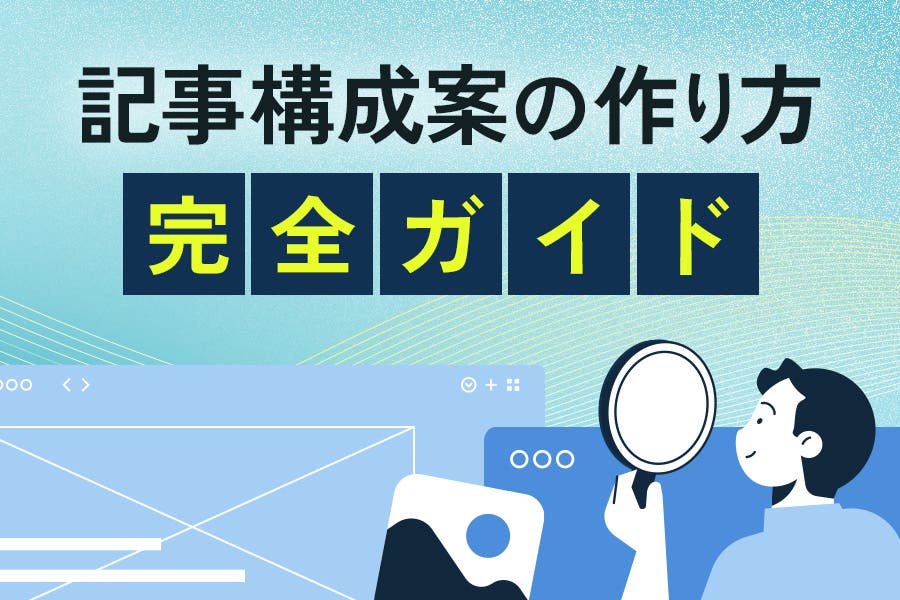
SEO記事の構成案を作るとなると、少し難しいイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。
でも、あまり難しく考える必要はありません。実際に大切なことは1つだけ、「読者が知りたい順番で、過不足なく情報を記載すること」で、それさえできていれば他は些細なことです。
理想論ではなく、事実として上位に上がるのは、検索エンジンに評価されようとキーワードをごちゃごちゃ入れたりした記事ではなく、読者と向き合った記事です。
この記事では、私が7年間コンテンツSEOをやってきて最も1位を取れた記事の構成案の作り方について、実際の流れに沿って解説します。
※この記事では、コンテンツ作成のステップのうち、ステップ2を解説しています。
| ステップ1. キーワード選定 | |
| ✅ | ステップ2. ニーズ調査・記事の構成案を作成 |
| ステップ3. 本文の執筆(SEOライティング)、公開 | |
| ステップ4. 効果測定・リライト |
読むのにかかる時間:約10分(合計5,600文字)
検索上位を目指すには、「そのキーワードを検索するユーザーが抱えている悩みや疑問に回答する」ことが何よりも重要です。そのため、いきなり記事構成案を作り始めるのではなく、ニーズを調査し、構成案を作る準備を整えましょう。
この準備は記事制作過程の1つですが、この工程で記事の精度が決まると言ってもいいくらい、とても大切な工程です。ぜひ丁寧に取り組んでみてください。
事前調査のステップ
それぞれ詳しく解説します。
顕在ニーズとは、消費者が自分自身で明確に認識しているニーズや欲求のことです。検索エンジン上で上位表示されるのはユーザーのニーズを満たしたコンテンツなので、どんなニーズを抱えているか調査することは最重要項目といえます。
キーワードにもよりますが、基本的に上位に表示されている記事は読者のニーズとある程度一致している記事、と考えて差し支えありません。実際に対策したいキーワードで検索して、現在の1位〜5位くらいの記事で扱われているトピックを確認してみましょう。もっと見るなら10位まで見ることもありますが、上位5記事を見ればほぼ目的は達成できます。
その中で、目安として2回以上扱われているトピックは、ユーザーが求めている情報である可能性が高いため、「含めた方がよいトピック」として書き出しておきます。
💡例えば…
「外国人 道案内」と検索すると、そのほとんどの記事で、道案内ですぐ使える便利なフレーズが紹介されています。道を聞かれた時のことや、今まさに聞かれていて知りたい!などのニーズが考えられますので、記事を作る際もそのトピックを含める方針で間違いはないでしょう。
さらに単語を1つ足して「外国人 道案内 失敗」と検索すると、上位記事では失敗した人の体験談が扱われており、実際のエピソードが知りたいというニーズが考えられます。この場合は体験談を集めてまとめたりした記事が、方向性として有効かもしれません。
仮にここに「外国人への道案内で失敗したあなたへの苦言5選」みたいな記事を作っても、そのワードで上位になることは難しいでしょう。別にこの検索をする人がそれを知りたくないからですね。
顕在ニーズはここまでの内容で把握できますが、これだけでは、表面的なニーズ理解に留まってしまい、競合サイトと差をつけることは難しいです。そのため検索上位に表示されるコンテンツを作るには、もうひと段階、深堀りしていく必要があります。
ここで大切なのが、潜在ニーズを捉えることです。潜在ニーズとは、消費者自身も自覚していないニーズ、または明確化されていないニーズのことをいいます。
例えば「英語 メール」というキーワードから考えられる意図は、真っ直ぐ考えると「英語でメールを送りたい!」になります(=顕在化しているニーズ)。しかし本当に英語でメールを送りたいだけであれば、検索ではなく翻訳アプリを開くのではないでしょうか。
つまり、顕在ニーズのさらに奥に、潜在的な別のニーズが存在している可能性があります。
潜在ニーズを捉えるには、ユーザーがどんな状態で検索しているのかを考えることが有効です。例えば「英語 メール」で検索する人は、どのような状態で検索していると考えられるでしょうか。
恐らく、
などの状態で検索していると考えられるでしょう。つまりこのキーワードには「センスがあると思われたい」「恥をかきたくない」などの潜在的なニーズがあると予想できます。
これらの潜在ニーズを満たすようなコンテンツを考えると、
などの要素を入れるのがよさそうです。顕在ニーズだけを見て作るよりも、ユーザーの本当の意図に寄り添ったコンテンツになりそうですよね。
ちなみに、少し前までこのキーワードで1位を取っている記事のタイトルは「センスが光る!英語メールの書き方・例文」という記事でした。潜在的なニーズを捉えた素晴らしいベストなタイトルだなと今でも思います。潜在ニーズを見事に突いたコンテンツは長らく1位に君臨していました。
このように表面から読み取れる顕在ニーズだけでなく、深掘りした潜在ニーズを踏まえてコンテンツを作ることが大切です。
💡ここまでのステップで、含めるトピックの洗い出し・そのトピックをどのような切り口で紹介するかを整理できていればOKです。
事前調査の最後のステップは、「その記事を読んだ人が、どうなっていたらベストか」という記事のゴールを設定することです。このあと実際に構成案を作成していきますが、ここで設定したゴールに向かって内容を組み立てていくことになります。
例えば、「英語 メール」というキーワードであれば、
のような、ユーザーの行動や考え方に変化が起きることをゴールとして設定します。
もしここで「メールの書き方がわかる」といった漠然としたゴールにしてしまうと、構成案を作成する際に「何がわかればOKなのか?」「どう伝えれば“わかった”ことになるのか?」といった、曖昧な問いに答えながら進める必要が出てくるからです。
また、自社ビジネスを商材として扱っているのであれば、記事のゴールは「商品の比較ポイントが理解でき、サービス資料をダウンロードしてみようと思える状態」などになるケースもあるでしょう。
いずれにしても、ユーザーがどんな変化を遂げるべきかを具体的にイメージしておくことで、より軸のぶれない、伝わりやすいコンテンツを設計できます。
ここまでのステップで、記事の内容自体は、もうかなりイメージが沸いてきませんでしょうか。ここからは、実際に記事構成案を作成していきましょう。含めるトピックは洗い出してあるので、そのトピックをどんな順番で、どのような粒度で解説するかを組み立てる作業です。
ポイントは以下の4つです。
ゴールから逆算して、「その状態に至るまでに、どんな情報や気づき、ステップが必要か」を考えた上で、記事の構成を組み立てていきます。
近年のSEO傾向を踏まえて、メインニーズから順に設計するという方法もあるのですが、例えばノウハウ系を伝えるコンテンツの場合、基本的には「前提 → 基礎 → 応用 → 実践」のように段階を踏ませる構成にすると、ゴールまでの道筋がクリアになります。
例)「英語 メール」をキーワードとする場合
ゴール:シチュエーションに応じた英文メールの書き方がわかり、実際に手を動かしてメールを作成できる状態
そのために必要な情報・ステップ
その他、比較検討系の記事であれば「導入→結論→比較軸の説明→商品紹介」という構成もよく見る設計です。競合他社の記事を確認するときも、どのような構成になっているかという視点を持ってみると、自社記事の改善点や読者にとって読みやすい設計に繋がります。
大枠の流れが作成できたら、流れに沿って見出しを作成していきましょう。見出しを作成する時は、H2、H3、H4を使い分け、入れ子構造を使って「見出しを読んだだけで記事の全体像が把握できる状態」になっていることが理想です。
以下に例を挙げているので、参考にしながら作成してみてください。
| ×悪い例 | 〇良い例 |
h2. 英語のメールの書き方 h2. 英語のメールを書くときの注意点 h2. ビジネス英語の例文 h2. メールのテンプレート | h2.英語でビジネスメールを書く前に知っておきたいこと h2.英語のビジネスメールの基本構成 h2.【シーン別】英語メールのテンプレート h2.よく使うフレーズ集 h2.さらにブラッシュアップするなら |
💡ポイント解説
悪い例では、「テンプレート」「例文」で見出しが分かれていますが、内容的には重複していて混乱のもとになります。また、本来「書き方」で紹介されるべき「件名の書き方」や「書き出しのパターン」などのトピックが別のセクションに含まれていることで、どの情報がどこにあるのか直感的にわかりません。
良い例では、最初に「ビジネスメールを書く前に知っておきたいこと」を紹介し、基礎知識や前提情報を提供しています。これにより、読者が後の内容をより理解しやすい流れになっています。また、h2→h3の階層構造できれいに情報が整理されているため、ユーザーが見出しを見ただけで必要な情報を探し出せるのも良い点です。
ここまでの内容を踏まえても、どちらのトピックを先に紹介すべきか迷ったら、流れに違和感がなければ「検索意図順」がおすすめです。端的に言えば、「読者が知りたい情報から書く」ということですね。
基本的に、ユーザーは早く自分の求めている情報を知りたいはずです。そのため、メインの検索意図を満たすトピックを先に持ってくるのは非常に理にかなっています。
このあとの注意点で詳しく紹介しますが、逆にメインニーズまでの距離が遠すぎると、読者が途中で離脱してしまう原因にもなりかねません。迷ったらメインのニーズを早めに提示することを意識してみてください。
見出しを階層構造で並べて違和感のない内容になったら、それぞれの見出しに概要を記載しましょう。
ライティングの際に「ここを意識する!」といった内容を記載し、どういった結論にするかを簡単でいいので書いておくと、ライティングの時に迷う時間が減るので結果的に時短になります。外注の際も「外注先によってクオリティがバラつく可能性」を減らせます。
不要な前提知識が含まれていたり、前提知識の情報量が厚すぎたり等の理由で、メインの検索意図を解決するまでに時間がかかってしまうケースがよく見受けられます。
例えばあなたが「冷蔵庫 おすすめ」で調べで記事をクリックした後、最初に「冷蔵庫とは?」などの出てきたら、絶対に読み飛ばすと思います。これは極端な例ですが、近しいことが様々なキーワードで起きている印象です。
記事を読み始めてから、なかなかメインニーズの解決に至らなければブラウザバックされて、直帰率や滞在時間、セッション継続時間が悪化して、トラフィックとランキングに影響を及ぼす可能性があります。
説明があった後に紹介があるというのは文章としてはとても自然なのですが、「ユーザーが知りたいのはあくまでのメインニーズについてである」ということを念頭に置き、
等の対応をすることをおすすめします。稀に「必要な情報か否かの見極めが難しい」と相談を受けることがありますが、その場合は一度公開してみて評価されるかどうかで判断するとよいです。
ユーザーのニーズに合った構成を組んでいけば、結果的にキーワードは見出しにも自然と含まれるはずです。ただし、語弊を恐れずに言うと、初心者の方ほど「言い換え」や「気の利いた表現」にこだわりすぎて、肝心のキーワードが見出しに入っていないことがあります。
検索エンジンは見出しの文言からページ内容を理解しているため、重要なキーワードを意図的に外すことは、SEO上マイナスに働く可能性があります。そのため、以下を意識しておくと安心です。
最終的には、「この見出しはユーザーの検索意図に合っているか?」と自問することで、SEO的にもユーザー的にも優れた見出しが作れます。
SEO記事で上位表示するには構成案がとても大切です。特に事前調査は、その記事が上位表示されるかどうかを決定づける重要なステップなので、時間をかけてしっかり行ってください。構成さえ完璧に出来ていれば、ライティングはそこまで難しくないのが正直なところです。
たくさん解説してあるので「大変そう……」と思うかもしれませんが、調査をしっかりと行えば、後工程がとても楽になります。その時間で成果が大きく変わるので、ぜひ根気強くやってみてくださいね。
正解のないものですので、ご自身で考えてより良い方法を探っていくことも大切で楽しいと思います。最後になりますが、迷った際は「読者にとって良い方」を選ぶことをおすすめします。
構成案が作成できたら、次は執筆をおこないます(=SEOライティング)。基本的には構成案の内容に肉付けをしていく作業になりますが、上位表示するにはいくつか押さえておきたいポイントがあるので、以下の記事で続きを確認してください。
次のステップ:構成案をもとに記事を執筆する