
【2026年版】SEOとは?SEO対策で上位表示するための具体施策と事例を解説
SEO対策
最終更新日:2026.01.05
更新日:2025.08.06
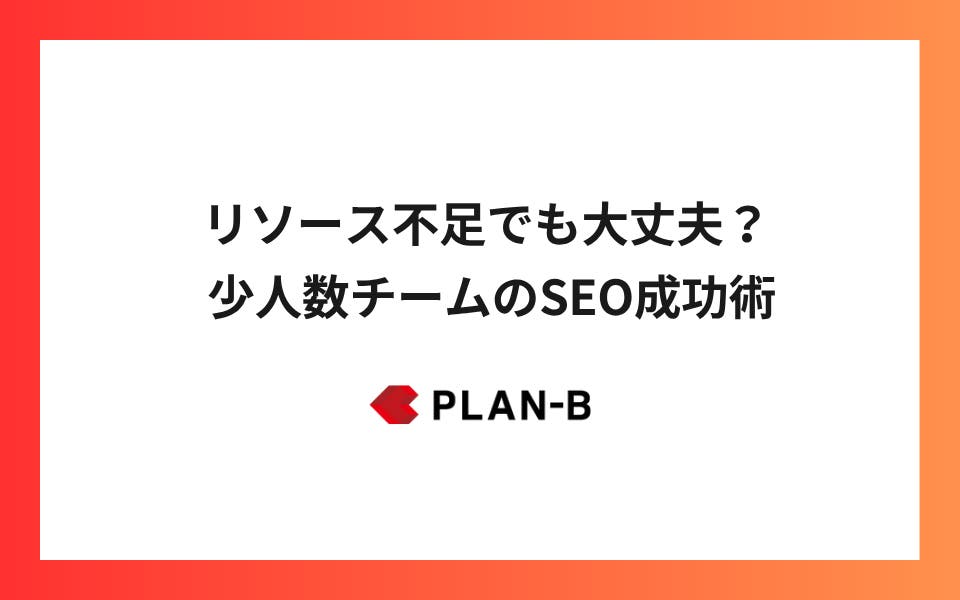
「SEOが重要なのは分かっている。でも、他業務に追われて手が回らない」
「やるべきとは思っているのに、着手する余裕がない」
日々の他業務に追われ、SEOの優先度が上がらないまま時間が過ぎていく。このような声は、少人数体制のマーケティングチームで特によく聞かれます。
では、少人数体制でSEOに本腰を入れて成果を出している企業は、限られたリソースの中で何をどのように施策を取捨選択しているのでしょうか。少人数でもSEOで成果を出す方法について、SEARCH WRITE事業部 プロダクトマーケティングマネージャーの松本に相談してみました。
本記事ではその様子をまとめています。ぜひご覧ください。
■この記事でわかること
少人数でも継続できる具体的な運用方法
SEOで成果を出す企業が実践する「目的意識」と「役割分担」の考え方
外注を活用する際に必要な「顧客理解」について
社内の役割と外注の役割の整理する方法
PINTO!編集部:SEOに取り組もうと思っていても、なかなか施策が進まない企業には、どんな特徴がありますか?
松本:短期的な目標を優先して、SEOの取り組みを後回しにしがちという特徴があります。たとえば「3ヶ月以内に○件のリードを取る」といった目先の成果を追わなければいけない場合、半年〜1年かけて育てるSEOの重要性は理解していても、優先順位を下げざるを得ないケースです。
PINTO!編集部:なるほど。SEOにおいて、「やるべき作業が分からない」という点も、運用が進まない要因ですよね?
松本:そうですね。何をやったらSEOで成果につながるかわからないは、あると思います。たとえば、筋トレをほとんどしたことがない人が、いきなり「理想の体を作って」と言われても、どんなメニューをどの順番でやればいいか分からないし、すぐに効果が出ないので「時間がかかりそう」「失敗しそう」と感じ、結果的に「今じゃなくてもいいか」と後回しにしてしまいがちです。SEOにおいても、無意識のうちに優先順位を下げているケースが多いと思います。
PINTO!編集部:たしかに、やるべきことがはっきりしないと、つい後回しにしてしまいそうですね。そうした「やるべきことの不明確さ」が、SEOが後回しになる大きな要因になりますか?
松本:まさにそうです。やるべきことが明確になっていないと、社内での説明や説得もしづらくなるため、ただでさえ「効果が見えにくい」「成果が出るまで時間がかかる」というSEOの特性が、さらにネガティブに捉えられてしまうんです。結果として、広告など即効性のある施策にリソースが偏ってしまい、SEOが後回しになってしまいます。
PINTO!編集部:SEOの重要性を理解していても、リソースに限りがある場合、何から着手すべきか迷う企業も多いと思います。どんな風に考えて着手すべきことを決めればよいでしょうか?
松本:まずは今やらなくてもいいことが何かを判断するべきです。たとえば、「仮説がない分析」は特にSEOの初期フェーズでリソースが限られる状況では避けるべきです。初期段階で細かい分析をしても、結局やるべきことは「記事を一定数作って蓄積する」など、大きくは変わらないケースがほとんどです。
PINTO!編集部:分析しても、実施するべきアクションが大きく変わらないので、最初は記事作成が重要ということですね。「仮説がない分析」は避けるべきとのことですが、そもそも「仮説が”ある”分析」とは、どんな分析ですか?
「仮説がある分析」というのは、文字通り「こうなっているのでは?」という仮説を持って分析することです。たとえば、「このキーワードは競合が強いから順位が伸びないのでは?」といった競合状況に関する仮説や、「タイトルを変えた記事のCTRは本当に改善したのか?」といった施策の結果を検証するための仮説などです。こうした仮説を立てることで、データを単に眺めるのではなく、具体的な次のアクションを考えるための分析ができるようになります。
PINTO!編集部:なるほど。具体的に「何を確かめたいか」がはっきりしているからこそ、分析が施策の改善につながるんですね。
初期フェーズにおいて、一見重要に思えるけれど実は捨てても問題ないものって他にもありますか?
松本:初期のうちは、問い合わせや資料請求などのコンバージョン数はあまり重視しすぎなくていいと思います。というのも、記事がまだ少ない段階だとそもそも流入自体が少なくて、コンバージョン数を見てもブレが大きく、正しい判断ができないからです。だいたい30本くらい記事が揃ってくると、ようやくデータとして参考にできるようになるので、まずはその30本を目標に、記事作成に集中するのが得策です。
PINTO!編集部:初期フェーズでの細かい分析やコンバージョン数の計測など、「必要でないことはやらない」と決めることがポイントなんですね。
松本:はい。SEOは「やるべきことがたくさんあり、すべてやれていることが理想的」というゲームで、そこに対してどの順番でやっていくかを決める必要があるため、裏返しにはなりますがやらないことを決めることが重要です。取捨選択ができないと、全てが中途半端になってしまう可能性があります。
PINTO!編集部:SEOを少人数で運用しようとしている企業は多い印象がありますが、運用する人が少なくても継続してSEOに取り組むための工夫はありますか?
松本:はい、少人数でもやり方次第で継続的に運用できます。一つ有効なのは、役割分担です。たとえば、キーワード設計担当が「今月5本」と決めキーワードを選定し、ライターが記事を書く。この役割分担があると、執筆も進みやすくなります。
PINTO!編集部:役割分担が、なぜ記事の執筆を進みやすくするのでしょうか?
松本:1人で全部を担当していると、「今週は忙しいから後回しでいいか」と判断してしまうんですよね。でも、キーワード設計と記事執筆を別の人が担っていると、「設計担当が今週分のキーワードを渡してきたから、週内に記事を書かないといけない」とか、「ライターが書き上げるのを前提に、次のキーワード設計も進めなければいけない」という相互のリズム、ある意味のプレッシャーが生まれる。
結果として、お互いがスケジュールを守る意識が働きやすくなり、施策実行が止まりにくくなります。
PINTO!編集部:なるほど。そうすると、理想的なのは設計担当とライターを専任で1人ずつ配置する体制なのでしょうか?
松本:必ずしも専任を1人ずつ配置する必要はありません。兼任でも「設計」と「執筆」を分担する仕組みがあると進めやすくなります。たとえば、月に4~6本記事を書くために、4〜6人で分担して、1人あたり月に1本程度を担当するような進め方でも十分です。負担は分散しながら、責任が放棄されないような体制にすることは、リソースが限られたチームでも着実に進めるポイントです。
PINTO!編集部:SEOにおいて役割分担が重要というのはよくわかりました。しかし、「分担」と言われても、そもそも社内リソースに余裕がなく、理想的な体制を組むのが難しいという企業も多いのではないでしょうか。
そういった場合、外注という選択肢が有効だと思いますが、外注で成果を出すためには何が必要か気になる方も多いと思います。実際にSEOを外注して成果を出している企業にはどんな共通点があるのでしょうか?
松本:外注で成果を出している企業には、まず「役割分担を整理している」、そして「顧客に関する情報をきちんと共有している」という2つの共通点があります。
一つ目の役割分担について、自社でやることと、外注に任せることが整理されていることが重要です。
たとえば、「誰に何を届けるか」といったターゲット設計やブランドトーンの最終チェックは社内で担い、記事構成・執筆・CMS入稿(※Webサイトの管理画面に記事を登録・公開する作業)などは外注するという分担体制をとっているケースがあります。このような自社と外部の役割を明確にした分担体制は、成果を出している企業に共通しています。
外に出しても問題なくクオリティが担保され、かつ社内でやろうとするとボトルネックになりうる作業を積極的に外に出せているとよいですね。
PINTO!編集部:外注においても役割分担を明確にしておくことは重要なんですね。
松本:二つ目の顧客に関する情報について、外注先にしっかり顧客情報を共有していることが重要です。
自社サービスに対して、誰が、どんな経緯で問い合わせや購入に至っているのかといった情報は社内にしか蓄積されていません。外注側がそれを把握できないと、顧客の課題や検討プロセスを理解できないので、どうしてもターゲットに届かない表面的なコンテンツしか作成できなくなってしまいます。
SEOにせよ、他マーケ施策にせよ、どのようなお客様がどのような購買行動を行っているかの解像度がなければ、戦略も戦術も筋が悪くなってしまいます。
実際、成果を出している企業は、次の情報を外注先に渡しています。
PINTO!編集部:なるほど。外注しながらも業務の質を高めるために必要なのは、顧客の声や検討プロセス、意思決定に関するリアルな情報なんですね。
PINTO!編集部:実際に外注を活用したい場合、どこまで社内で行い、どこから外部に頼れるのかイメージが湧かない企業も多いと思います。一つの例として、PLAN-Bの「戦略設計・施策代行プラン」では、どのような支援体制を提供しているのでしょうか?
松本:社内に、SEO経験者と専任ライターを1人ずつ配置するのと同じくらいの推進力を提供しています。その力を最大限活かすために、支援を始める前には必ず「お客様側の役割(顧客情報の共有やコンテンツの最終チェックなど)」と「PLAN-Bの役割(キーワード調査、構成案作成、執筆、入稿、進行管理などの実行部分)」を明確に分けた上で、SEOの目的や戦略を一緒に整理します。
こうして役割分担を決めたうえで、実行に必要な調査から入稿・進行管理までを一貫して支援し、成果につながるコンテンツを着実に積み上げる仕組みを提供するイメージです。
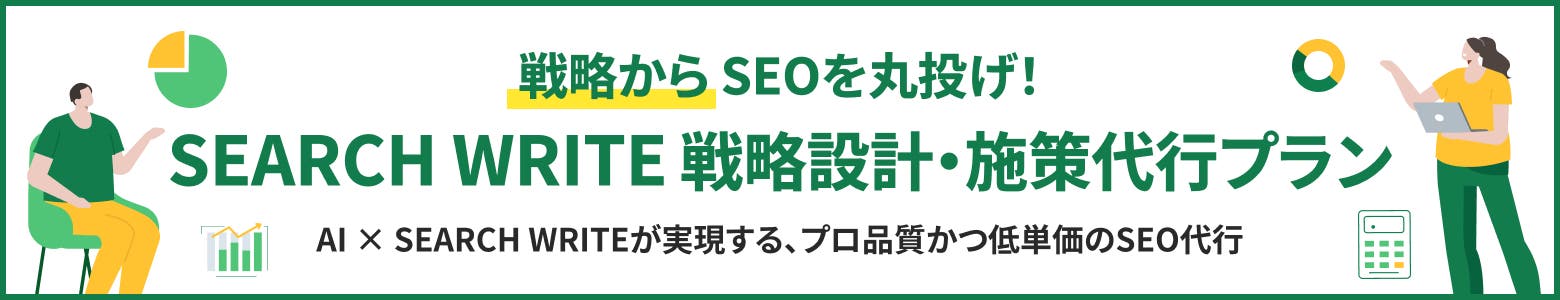
PINTO!編集部:
今日のお話を通じて、少人数チームでもSEOで成果を出すには、以下の3つがとても重要だと理解しました。
松本:
その通りです。あれもこれも手を出すのではなく、たとえば初期の細かな分析やCV指標のように、いったん脇に置いてもいいものを見極めることが、継続と成果につなげる第一歩です。
PINTO!編集部:
「全部やる」ではなく「続けられる形を設計する」という視点が、大切なんですね。本日は大変勉強になりました。ありがとうございました!
松本:
こちらこそ、ありがとうございました。いつでも気軽にご相談してください!
■記事内容まとめ
成果を出す企業は、初期段階ではCVよりも記事作成に集中し、役割分担(設計+ライターなど)やリソース確保で運用を継続している。
外注活用では、自社と外部の役割分担の整理と、自社の顧客に関する情報の共有が鍵。
「実行部分は外部」、「記事チェックは社内」などと分担し、SEO運用の推進力を上げる。
「SEARCH WRITE 戦略設計・施策代行プラン」では、SEO経験者とライター1名分の推進力を提供。目的に沿ったキーワード調査から記事公開まで、少人数体制でも運用を支える仕組みが整っている。