
【5分でわかる】GTM(Googleタグマネージャー)の設定方法
Web広告
最終更新日:2025.02.03
スライドショー広告は、その名の通り複数の静止画を順次表示する形式の広告です。
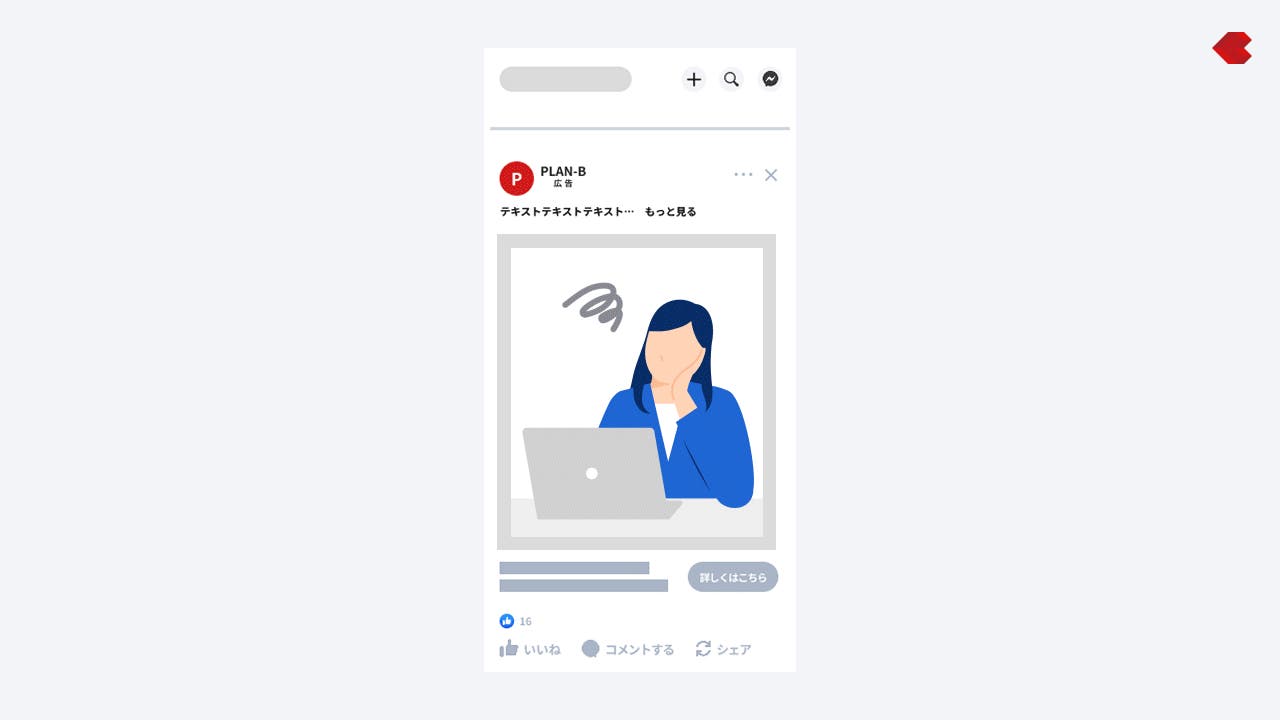
配信先のプラットフォームやデバイスに応じて、レイアウトやフォーマットが最適化されるため、スマートフォンやタブレット、パソコンなどさまざまな環境で一貫した表示が可能です。
画像が切り替わるタイミングは広告を出す際に設定でき、ユーザーはスムーズにスライドショーを閲覧することができます。
配信後はスライドごとのパフォーマンスを把握することができ、必要に応じて内容の調整を行うことが可能です。
スライドショー広告は、動画広告と比べて制作にかかる費用や時間を大幅に削減できる点が大きな強みです。
動画広告の場合撮影から編集、さらには音声や特殊なエフェクトの追加などが必要になるため、全体の制作コストが高くなってしまいます。それに対しスライドショー広告は静止画を組み合わせれば制作できるため、複雑な工程が不要です。これにより制作期間や費用が削減できます。
さらに動画のように複雑なエフェクトを用いなくても、十分に訴求することが可能です。
また動画と比べると内容の調整にかかる工数が少なく、A/Bテストなどの検証がしやすいことも強みとして挙げられます。
このように、スライドショー広告は予算や工数が限られている場合でも挑戦しやすい広告だといえます。
スライドショー広告は複数の画像が連続して表示されるのみで単調であるため、ユーザーが途中で飽きてしまう場合があります。
コンテンツが自動で切り替わるため、気づいたら注意が他に向いてしまうことがあります。一方で各スライドの表示時間が速すぎれば情報が伝わらず、遅すぎれば逆にユーザーの興味を削いでしまいます。したがって、適切な表示時間(3~5秒程度)を意識して調整することが重要です。
さらにスライド間の切り替えがぎこちなくなると、視聴体験が悪くなりユーザーの集中力が低下します。
また画像の内容が単調だと、ユーザーがすぐに飽きを感じる恐れがあります。全体のストーリーを通じて一貫したメッセージが伝わるように設計することも、ユーザーの興味を持続させるポイントです。
ユーザーに最後まで見てもらえるよう、適切な表示時間やスムーズな切り替え、ストーリー性をもたせることを意識しましょう。
スライドショー広告は複数の画像を連続して表示する形式であるため、動画広告と比べると表現の幅に制約があります。
動画広告は音声や動き、エフェクトを活用して幅広く表現することができます。一方スライドショー広告は画像が主体であるため、細かなニュアンスを表現するのが難しいです。そのためスライドショー広告では、複雑な情報やメッセージを十分に表現しきれない場合があります。
さらにエフェクトやアニメーションを使うことが難しいため、視覚的なインパクトが少ないといえます。
スライドショー広告では、ユーザーに具体的な行動を促すためのCTAの配置が特に重要です。
※CTA…「今すぐ登録」などの、ユーザーに特定の行動を促すための指示やボタン、リンクなどを指す。
例えば最終スライドにCTAを配置すると、ユーザーが商材の全体像を把握した後にコンバージョンなどの行動を起こしやすいです。一方一枚目の画像にCTAを配置すると、ユーザーがまだ十分な情報を受け取っていない状態であるため、コンバージョンを獲得できない可能性が高いです。また複数の画像に分散してCTAを配置すると、どのボタンをクリックすればよいのか分かりづらくなり、効果が薄れてしまう可能性があります。
そのためCTAを目立つようにしながら、広告全体のデザインやストーリーを損なわないよう工夫することが必要です。ボタンの色やサイズ、位置など細部にわたるデザインを意識しましょう。