
【アフィリエイト初心者向け】おすすめASP20種を紹介
Web広告
最終更新日:2025.02.13
更新日:2022.12.23

オムニチャネルは近年マーケティング業界で、注目度が上昇している販売戦略の1つです。
これまで主流であったマルチチャネルやクロスチャネルを、さらに一歩進化させた概念でもあります。
オムニチャネルを取り入れていかなければ、今後生き残り続けるのは難しくなるでしょう。
この記事では、オムニチャネルの概念や導入のためのメリット、成功のためのポイント、成功事例などを紹介しています。

そもそもオムニチャネルとは、どのような販売戦略を指すのでしょうか。
マルチチャネルやクロスチャネルとの違いにも注目して意味を理解しておきましょう。
「オムニ」は「すべての…」という意味をもつ言葉です。
「流通販路」を表す「チャネル」と接続することにより、「すべての流通経路」を表す合成語となります。
実店舗やECサイト、カタログ通販、ソーシャルメディアといったさまざまなチャネルを連携させ、より顧客にとって利便性の高いサービスを実現するためのマーケティング手法なのです。
そもそもオムニチャネルが誕生したのはなぜなのか、その背景を確認してみましょう。
「オムニチャネル」という言葉が誕生したのは2011年、アメリカのメイシーズという百貨店がオムニチャネル宣言を発した時です。
当時世界ではAmazonなどのインターネットを介した流通販路が主流となっていた中で、百貨店はショールーム化してしまい、著しく業績が落ちていました。
その流れは加速する一方だったので、何も手を打たなければ百貨店の業績は時間と共に縮小し、廃業を待つだけとなってしまいます。
その状況に待ったをかけるべく、メイシーズが膨大なシステム投資により、実店舗とECサイトの垣根をなくすというマーケティング戦略に打って出ました。
それにより顧客情報を一元管理して、顧客一人ひとりのニーズを的確に把握できるようになったのです。
さらに売れ残り在庫の圧縮や売り場の効率化にも繋がり、メイシーズの業績は見違えるほどのV字回復を見せることとなりました。
メイシーズ以降、多くの小売店もオムニチャネル化を推進し、IT時代のWebマーケティング戦略としてオムニチャネルが主流な手法となったのです。
マルチチャネルは顧客に対して、実店舗やECサイトなど複数のチャネルを提供することを指します。
オムニチャネルとの決定的な違いは、それぞれに垣根があり独立した運用をしているということです。
そのため、各チャネルで得た情報が同期されることはありません。
顧客としても購入するチャネルごとに個人情報を登録しなければならず、それぞれIDやパスワードを管理しなければならないという負担が生じます。
たとえば同じ学校に複数の数学の先生がいるものの、生徒の情報がまったく共有されていないような状況がそれにあたります。
生徒は質問のたびに自己紹介をしたり、自分の苦手分野を説明したりしなければならず、不便さを感じてしまうことでしょう。
このような体制では、効率的に顧客(生徒)のニーズに応えることができなくなります。
マルチチャネルの顧客側のデメリットを説明しましたが、実は販売者側にもあります。
チャネルが多角化すると、チャネルごとの在庫管理が難しくなり、過剰在庫によるロスや在庫不足による機会損失が発生するというリスクもあるのです。
クロスチャネルは、それぞれのチャネルを背後で連携させることにより、顧客情報を一元管理するという手法です。
ただしクロスチャネルには「無駄をなくす」という効果はあるものの、顧客に最大価値を提供するという部分では効果を発揮できません。
オムニチャネルでは、顧客がどのチャネルを利用した場合であっても最適なサービスを提供できるように環境が整えられており、その点がクロスチャネルとの大きな違いであると言えます。
切り口は若干異なりますが、オムニチャネルはO2O施策と混同されることもあります。
O2O施策は「Online to Offline」の略語。
簡単に言えばECサイトなどのオンライン販路から、実店舗などのオフライン販路へと顧客を流すための施策です。
具体的なO2O施策としては、ECサイト上で実店舗のクーポン券を発行するといった手法があります。
このO2O施策は、オムニチャネルと意味が異なるというものではなく、オムニチャネルの手法の1つです。
O2O施策も含めたさまざまな施策を提供し、顧客にさまざまな価値を提供することが、オムニチャネルの目指すところです。

企業がオムニチャネルを推進することで、さまざまな効果を得ることができます。
具体的な効果としては、主に以下の3つです。
それぞれ詳しく解説していきます。
オムニチャネル化により、顧客は利用するチャネルに関わらず、自分のこれまでの購入履歴やインターネットの閲覧履歴などに従って最適なサービスを受けることができます。
最近は特に商品を購入するつもりがなくても、インスタグラムでいいねしたり、YouTube動画を見たりすることもあるでしょう。
そのような行動もすべて情報として一元的に管理され、よりパーソナライズされた商品やサービスの情報が提供されるようになるのです。
よって顧客としては、自分に最適な商品・サービスをわざわざ検索するという手間がなくなります。
その結果、購入に至るまでの工数や意志決定回数を削減することができ、満足度が上昇していくのです。
オムニチャネルの最大のポイントは、各チャネルの垣根が取り払われ、それぞれで得た情報が統合して管理されるということです。
そしてそれぞれのチャネルで得られた情報は、ただ上に積み重ねられるというだけではなく、掛け合わされることによってより大きな効果を発揮することができます。
このシナジー効果が発揮されることで、さらに顧客の満足度も高まっていくのです。
オムニチャネルにより利便性が高まれば、現在は購入を考えていない潜在的な客層も取り込むことができます。
中長期的な目線で見れば、より多くの顧客を獲得することにも繋がるでしょう。
また、実店舗の場合はその商圏にいる住人しか客層として取り込めないものの、ECサイトを立ち上げることで遠方の顧客を獲得することもできます。
このようにオムニチャネル化には、購入者の裾野を大きく広げていくという効果もあるのです。

これからの時代、オムニチャネル化を進めていかなければ、競争で大きく後れを取ってしまうことは間違いありません。
しかしだからと言って、「とにかくオムニチャネル化だ!」と無計画に進めても失敗に終わる可能性が高まります。
そこで実際にオムニチャネル化を進めていく際に意識したいポイントを4つ解説します。
ロードマップの策定は、オムニチャネル化に限った話ではなく、新しい事業を始めるためには不可欠です。計画なくして正しい方向に進むことができません。
確かに、「とにかくやってみて考える」ことも大切でしょう。
しかしオムニチャネル化はかなり大規模なシフトチェンジにもなるため、社内の限られたリソースを最大限有効に活用するためにも、しっかりとしたロードマップの策定が求められます。
具体的にロードマップに織り込みたいのは
といったような内容です。
具体的な数字で規定しておかなければ、社内メンバーでの共有を図ることも難しくなります。
他の事業の進行状況、そして自社を取り巻く社外の環境なども考慮しながらロードマップを策定しましょう。
オムニチャネル化は会社が一体となって進めていかなければならない施策です。
多くの場合、販売チャネルによってそれぞれの部門が設けられているでしょう。
しかしオムニチャンネル化を成功させるためには、部門ごとの垣根や壁を取り払ったチームを編成する必要があります。
縦割りの場合、どうしても部門間がギスギスして思うように協力関係になれないという懸念もあります。
実店舗を統括する部門から見れば、オンラインの販売施策を強化することで自分たちの売上をオンライン販売部門に取られてしまうというように考えてしまうためです。
しかしそれはオムニチャネル化推進にあたっての癌にしかなりません。
部門同士の協力ができなければ、「チャネル間のシナジー効果を発揮して顧客に最適なサービスを提供する」というオムニチャネル最大のメリットが得られなくなります。
少し精神論っぽくもなりますが、会社のメンバー全員が同じ方向を向いていなければ、事業が成功することはありません。
まずは根本的な社員の意識改革も含めて、社内体制を抜本的に整備する必要があります。
オムニチャネルで最も重要なことは、各チャネルが有する情報を一元的に管理することです。
チャネルごとに得られた情報を集約し、顧客それぞれの個性を分析することで、より最適なサービスや商品を提供できるようになります。
マーケティング部門だけではなく、IT部門との連携も不可欠です。
インターネット上の閲覧履歴や購入履歴、ポイント獲得履歴などは比較的簡単に統合できるものの、実店舗などオフラインで得た情報はなかなか統合しづらい部分もあります。
しかし、「どのスタッフが対応した時には購買に繋がった」「話の中で得られた顧客の好み」など、必ずしも数値データには現れない情報も少なくありません。
そしてそういったオフラインで得られる情報こそ、実は非常に重要であるということもあります。
その情報を漏らさずデータ化するためにも、店舗にタブレット端末を導入するなど、顧客管理システムを構築することが大切です。
このシステムを構築することで、従来はレジでの会計時にPOSシステムでしか得られなかった情報に加えて、より具体的かつより効果的な情報を得られるようになります。

2011年のオムニチャネル宣言以降、日本国内でもさまざまな企業がオムニチャネル化を実施し、成果を収めています。

公式サイト:https://www.muji.com/jp/passport/
無印良品を展開する良品計画は「Muji Passport」というアプリを活用し、オムニチャネルに取り組んでいます。
このアプリには、欲しい商品の在庫を店舗ごとに検索できるような、便利な機能があります。
ほかにも「Muji Passport」を導入することで、利便性の向上を含めたさまざまな顧客体験を提供することができるようになりました。

公式サイト:https://www.tokyu-dept.co.jp/
東急百貨店はTwitterやFacebookなどのソーシャルメディアを活用して積極的にオムニチャネルに取り組んでいます。
公式スマートフォンアプリの「東急百貨店」もリリースし、店舗のフロアマップとして利用できたり、アプリからのショッピングができたりするのも大きな魅力です。
通常のチラシやDMで来店者が貰えるクーポンのコンバージョン率が5%のところ、アプリとの連携により20%に達したという実績もあります。
このケースでは、オムニチャネルによる効果が大きく出ていることがわかります。

事例ページ:https://orange-pos.jp/works/komehyo.html
ブランドリユースストアのKOMEHYOは、Orange POSの導入を行いました。
この取り組みには「豊富な商品知識を持ち合わせたスタッフの接客」をさらにスムーズにし、顧客満足度を高める目的がありました。
Orange POSの導入により、顧客のニーズに沿った柔軟なカスタマイズによる提案が可能となったのです。
わざわざレジでの会計を行う必要性がなくなったことで、接客クオリティの向上にも繋がるなどの大きな効果をもたらしました。
ほかにも楽天ポイントとの連携、豊富な決済手段への対応、多言語対応など顧客に多くの利便性を提供しています。
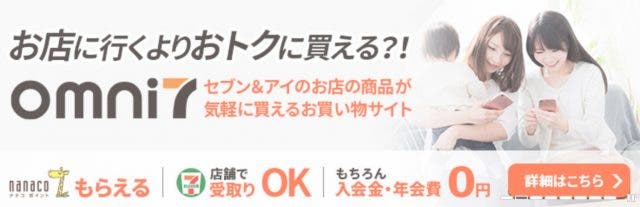
公式サイト:https://www.omni7.jp/top
セブンイレブンやイトーヨーカドーなどを展開するセブン&アイホールディングスは、オムニ7と銘打ったオムニチャネルを展開しています。
オムニ7ではECサイトで購入した商品を、近所のセブンイレブンで受け取ることが可能となりました。
またサービス利用時に発行されるポイントを他店での買い物でも利用できるようにもなり、利用者はより便利にセブン&アイホールディングスでの買い物を楽しめるようになりました。
時代の変化と共に商品やサービスの販売の在り方も大きく変化しています。
ITが進展し、Webでのマーケティングが重要視されるようになった現代は、オムニチャネルにより多くのチャネルを統合してマーケティングを行うことが非常に重要です。
顧客としては当然、より利便性の高い方法を好みますから、オムニチャネルに対応できない企業は次第に淘汰されていくでしょう。
もちろん予算の都合や業態の都合などにより、必ずしもオムニチャネルが必要になるとは限りません。
しかし単に「クオリティの高い接客スキル」といったような属人的な能力だけを売りにしていると、十分なリピートや新規顧客獲得につなげることは難しいでしょう。
その意味でも、オムニチャネルによりシステム(制度)としてマーケティング体制を整えることが、現代の最重要施策であると言えます。