
【アフィリエイト初心者向け】おすすめASP20種を紹介
Web広告
最終更新日:2025.02.13
更新日:2022.12.23

D2C(DtoC:Direct to Consumer)とは、メーカーやブランドといった製造者が直接消費者と販売取引を行うビジネスモデルを指します。
流通や卸売、小売といった中間業者を介さないためコストが削減できるだけでなく、消費者と直接関係を持てるため、顧客データを蓄積しやすいメリットがあります。
最近ではインターネットの普及やEC市場・SNSの拡大とともに、アパレルや化粧品といった実体のあるモノを扱う企業でもD2Cを導入する例が増えています。
今回はD2Cの概要から、メリット・デメリット、国内外の成功事例を紹介します。

D2C(DtoC)とはDirect to Consumerの略であり、メーカーやブランドといった製造者が直接消費者と販売取引を行うビジネスモデルを指します。
D2Cでは仲介業者(流通や卸売、小売など)を介さず、メーカーやブランド自ら製品企画・製造を行い、完成された製品を自社のECサイトで消費者へ直接製品の販売を行っていきます。
商品の企画から製造、販売や顧客へのアフターフォローなど、すべての工程を自社で担当する点が、従来の通販と大きく異なる部分です。
流通や卸売、小売といった中間業者を介さないためコストが削減できるだけでなく、消費者と直接関係を持てるため、顧客データを蓄積しやすいメリットがあります。
このほかにもブランドを最重要視したプロモーションや顧客へのフォローを行い、ファンを増やすことで爆発的に売り上げを伸ばせるといった特徴も。
インターネットの普及やEC市場・SNSの拡大に伴い、近年ではぞくぞくとD2Cを導入する企業が増えているのです。
ではより詳しくD2Cが注目を集める背景と、「BtoB」「BtoC」「CtoC」との違いをお伝えします。

D2Cは2000年代の後半から徐々に注目を集めはじめた用語ですが、形態自体に真新しさは、実はありません。
注目を集めるようになった背景には、実体のある商品を扱う企業にも、EC市場やSNSの発展により、D2Cを採用しやすくなったことが挙げられます。
かつてD2Cのようなビジネスモデルを取れた業界は、デジタル上でサービスを提供できる一部の企業に限られていました。実体のある商品を扱う企業は、小売店や卸売など、決まったチャネルを経由して商品を販売するのが一般的な方法でした。
しかしEC市場やSNSの発展により、アパレルや雑貨といった実体ある商品を提供する企業もD2Cの形態を採用しやすくなりました。
仲介業者を介す必要がないことからコストを大幅に削減でき、かつ自社のファンとの結びつきを強められるD2Cのメリットを踏まえ、多くの企業にD2Cは広がっていったのです。
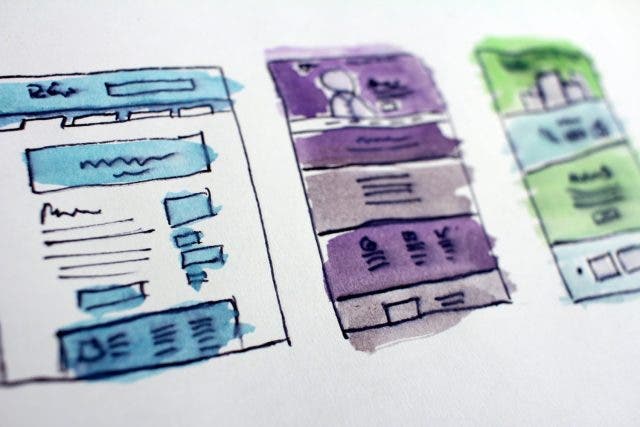
よくD2Cの文脈で出てくる、BtoB,BtoC,CtoCといったマーケティング用語との違いもあわせて確認しましょう。
BtoBとは、企業間での取引を指します。
具体的には、製造業者(メーカー)と卸売業者や小売業者など企業と企業で、商品(サービス)をて提供するビジネスモデルです。。
パソコンを製造するメーカーが、必要な部品を業者から仕入れ購入する場合などは、まさにBtoBのケースに当てはまります。
BtoBはターゲットや取引先が限定されている場合が多く、消費者向けのような流行などは、業種によってはそこまで左右されない可能性が高いといえるでしょう。
BtoCとは、企業が消費者向けに行う取引のことを指します。
取引といわれると仰々しく感じられるかもしれませんが、これは私たちが普段買い物をすることそのもののスタイルです。
コンビニやスーパーなど店頭で買い物をすることもそうですし、ホテルやレジャー施設などを個人で利用する場合にも当てはまるでしょう。
ほかにもAmazonや楽天市場などオンライン上のECなども、BtoCのビジネスモデルに当てはまります。
BtoCはBtoBとは異なり、ひとつの取引自体の受注単価が低いほか、消費者の趣向やトレンドに左右される事も少なくありません。
製造者と消費者が直接関わりをもつD2Cと異なり、BtoCは製造者が自ら消費者と関わることなく、間に仲介業者が介在しています。
CtoCとは、一般消費者と一般消費者が直接やり取りを行う、個人間取引を指します。
かつてCtoCといえば、フリーマーケットが代名詞でした。
しかし最近ではメルカリなどのフリマアプリやヤフオクなどのサービスが、以前よりも広く利用されるようになりました。
またミンネやCreemaといった個人製作のハンドメイド品を個人に向けて販売するサービスなども、人気が高まりつつあるCtoCサービスです。
それぞれ市場規模も拡大しつつあり、オンライン上でもさまざまなCtoC形態のビジネスモデルが登場してきているのです。

D2Cのメリットは主に以下の3点が挙げられます。
D2Cのメリットを最大限活かすためにも、効果的なSNSの活用が重要であるといえるでしょう。
まず一つ目のメリットは、仲介業者を介さないため中間コストが削減できるという点です。
従来の販売モデルの場合、製造後の卸や販売などは、中間業者や仲介業者を利用する流れが一般的でした。
当然外部へ依頼することとなるため、そこにはコストがかかってきます。
一方、D2Cのビジネスモデルでは、商品の企画から開発、製造や仕入れ、そして販売や発送までをすべて自社にて行います。
製造元の企業が直接一般消費者に商品を販売することで、流通や卸売、小売、大規模ECといった、仲介業者を介す必要がありません。
そのため手数料などの中間コストを大幅に削減でき、より適正な価格に下げたり、製品の品質の向上に費用をかけたりといった工夫が行いやすくなります。
D2Cの二つ目のメリットとして、顧客データを社内にストックできる点が挙げられます。
従来であれば間に中間業者が介在しているため、製造・流通・販売のそれぞれの段階で個別にデータを集める必要がありました。
大規模ECを活用する場合は顧客データは管理できますが、特定のポータルサイトでのみ閲覧可能であるなど、自由度が高い設計とはなっていません。
しかしD2Cであれば全ての工程を一括して自社で行うため、社内に顧客データを保有でき、細かな顧客分析が可能になります。また部門を越え社内全体で顧客データが閲覧しやすい環境も、D2Cの場合は構築しやすいといえます。
顧客の属性や購入履歴、EC内での動きを把握することで、より効果的なキャンペーン施策や新商品開発につなげられるでしょう。
D2Cはメーカーと一般消費者が直接つながることから、SNSと相性が良いとされています。
D2Cのメーカーがマーケティング戦略としてSNSを併用していくと、エンゲージメントが高いファンを獲得しやすいメリットがあります。
自社でSNS運用を行うことで、一般消費者に直接ブランドや商品のメッセージを具体的に伝えることが可能になることが大きな理由です。
またSNSではコメントなどの双方向なコミュニケーションが、より手軽に行えるといった特徴もあります。これにより一般消費者に対し身近な存在に感じてもらいやすく、自社サイトへの誘導が容易に行えるようにもなります。
SNSを上手に活用することでブランドイメージを高めて世界観を提示できれば、メーカーやブランドにファンがつき、継続的な購買につながりやすくなるメリットが強いのです。

欠点のなさそうなD2Cですが、実はデメリットも存在します。
デメリットもきちんと理解した上で、効果的な販売戦略を練っていきましょう。
一つ目のD2Cにおけるデメリットとしては、初期費用がかかりやすい点が挙げられます。
D2Cでは製造から流通、小売までをワンストップで自社内で行なっていくため、初期段階にそれらの仕組みを構築する必要があります。
初期投資がかかる分、払ったコストが回収するまでにある程度の時間を要する場合が多いでしょう。
また流通や販売、サポートなどの仕組みづくりも自社で行わなければなりません。
この仕組みづくりには、費用だけでなく時間や人員的なさまざまなリソースを必要とするため、この点もデメリットになりうる可能性があるでしょう。
どの部分も外注化することが可能なのですが外注をした分コストもかさみ、自社の手の届かないところで動いてもらうことになるので管理コストもかかるといったデメリットもあります。
D2Cのデメリットとして、宣伝・マーケティングにより緻密な設計が必要である点が挙げられます。
大規模ECは利用者も多く、特集や類似商品のおすすめ訴求など、様々な工夫が凝らされていることから、消費者への認知が比較的簡単にできる特徴があります。
しかしD2Cは上記のような大規模ECを活用する上でのメリットを享受できません。
おまけにD2Cでは、先ほど述べたようにEC開設といった初期費用も膨大にかかります。
その上に認知拡大に向けて、緻密な宣伝・マーケティング戦略の設計を行う必要があるため、特に初期の段階は難しい部分も多く、D2Cマーケティングに精通しているプロとともに戦略を練るのがおすすめです。
では実際に海外・国内でどのような企業がD2Cを導入し、成功させているのでしょうか。
今回はアメリカ・中国・日本の成功事例を紹介します。
はじめに紹介するアメリカのアイウェアブランド Warby Parkerは、D2Cをいち早く導入した企業として有名です。
2010年にペンシルバニア大学に在籍していた学生4人で設立されたWarby Parker。製造と販売にかかわる中間業者を排除したD2Cのモデルで、アイウェアをオンライン上のみで販売を開始しました。
企画はもちろん自社で行い、デザイナーも社内に抱えてスタート。スマホ上で擬似試着が楽しめるアプリも開発されており、気軽に自分好みのメガネを探すことができます。
自社ブランドに対する意識も非常に高く、PRやブランディング戦略にも力を入れてきました。
2015年にはGoogleやAppleなどの名だたる企業を抑え、『世界で最もイノベーティブな50社(THE WORLD’S 50 MOST INNOVATIVE COMPANIES)』において堂々の1位を記録。
そんなWarby ParkerはSNSなどを駆使したマーケティング戦略等に強く、2020年6月現在、インスタグラムのフォロワー数は55.8万人にも。口コミから購入を決める顧客が多いのが特徴です。
中国では完美日記(Perfect Daily)と呼ばれるコスメブランドが10〜20代女性から圧倒的な支持を受けています。
中国で多くの人に利用されている小紅書(RED)というSNSでは、197.2万人ものフォロワー数を誇る完美日記(Perfect Daily)。
販売から数年でロレアルやGIVENCHY、資生堂といった国際的に名高いコスメブランドと肩を並べるようになりました。
小紅書(RED)にはECも連動されており、一般消費者は芸能人やインフルエンサーの投稿から、すぐに商品を購入できるようになっています。
完美日記(Perfect Daily)がここまで短時間に認知拡大できた背景には、小紅書(RED)を中心としたSNS上で芸能人やインフルエンサーによるマーケティング戦略が大きく影響しているといえるでしょう。
公式サイト:https://bulk.co.jp/
BULK HOMMEは2013年からスタートした、男性向けスキンケアブランドです。最近では木村拓哉氏が出演するCMが放映されるなど、注目度が高まっています。
BULK HOMMEは、今まで主流でなかった男性のスキンケアに特化し、新たなカルチャーを作り上げようとしているブランドでもあります。
BULK HOMMEでは「メンズスキンケアで世界一を目指す」をモットーに、本当に自分たちにとって良いメンズスキンケア商品を世界基準で追求し、製造・販売しています。
品質の高さと秀逸なブランディング力から、瞬く間にブランド認知が広がり、韓国や中国、台湾にも展開されることに。
今後はヨーロッパ進出も行われる予定で、今、日本で男性向けスキンケアブランドを牽引している存在だといえるでしょう。
今回はD2Cの概要から、メリット・デメリット、国内外の成功事例を紹介してきました。
D2Cを採用する企業は今後もますます増えていくと予想されます。またD2Cビジネスを成功させるためには、効果的なSNS活用が非常に重要となってくることでしょう。
SNSマーケティングでは、インフルエンサーを活用したマーケティング方法が効果が高いといわれています。インフルエンサーの選定や活用方法が知りたい場合は、インフルエンサーマーケティングに詳しいマーケティング会社に相談するのもおすすめです。