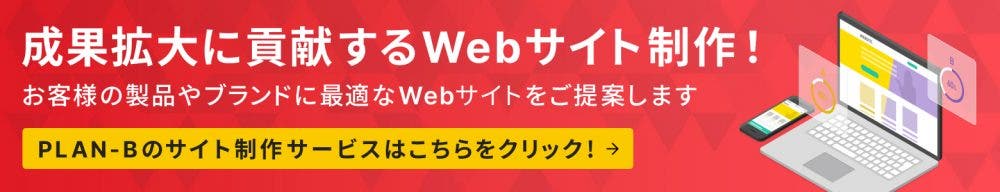Webサイトで使用される定番フォント9選! フォントの選び方や良いフォントの特徴も解説!
Webサイト制作
最終更新日:2023.05.11
更新日:2023.03.14

突然ですが皆さん、ライセンスのお話はお好きでしょうか?
何となく避けてしまいがちなライセンスのお話。私も含め多くのWeb制作に携わる方が「面倒くさい・多すぎて意味不明」などと思っていることでしょう。ぶっちゃけいいますと、特段詳しくなる必要はなく、正しい判断が欲しければ専門家に委ねればいいわけです。
ただ何も知らないというのは無知蒙昧。Web制作に携わる者であれば是非ともさわりぐらいは知っておきたい所です。というわけで、今回は特にデザイナー・エンジニアに関係してくるライセンス周りについてまとめてみました。
ざっくりと一言で説明するなら「利用者が守らなければならない決まりごと」です。色々難しい言葉で説明されていたりしますが、要するに「利用するならこのライセンスで定義された決まりごとを守ってくださいね。守らないと著作権法の下で罰則が適用されるので注意してね♪」ということです。
ライセンスは著作権者が著作物に対して付与できるルールのようなもので、実世界・Web世界関係なく一般的に利用規約という形でも存在します。
Webの世界では基本的に実体が無い「ソフトウェア」や「メディア」や「サービス及びツール」などにライセンスが付与されるわけでして、しかもその利用者の範囲がワールドワイドになるため世に出す前に正しいライセンスを付与し、著作物を守らないと取り返しがつかないことになりかねません。
Webの性質を考えれば当たり前の話ですね。ただ前述したように、実体がなく色んな性質を持つ成果物に付与されるだけあってライセンスの数も多く、しかもその内容も多種多様な考え方に基づいて発展してきた歴史があります。
ここがややこしく、何となく「面倒そう」と思わせてしまう所だったりするわけです。
Web制作者であればGIFやJPEGを日常的に使うことも多いですが、この広く一般的に使われている画像フォーマットにもかつてはライセンスに関するいざこざがありまして、訴訟問題を避けるために利用を控えた時代があったりしました。
ちなみにGIFライセンス問題の影響で代替として誕生したのがPNGだったりします。
(参考:GNUのウェブページにGIFファイルが一つも無い理由)
またJPEGに関しても「2次元ランレングス符号化」の特許を取得していたForgent社が、ソニーを含む家電メーカーに対して使用ライセンス料を求めた裁判合戦があり、31メーカーに対して合計1億1000万米ドル以上のライセンス料の収益があったとされています。
今ではそのいざこざも収束し特に問題なく利用できるわけですが、かつてはそういった時代もあったと思うとやはりライセンスって意外と身近な存在にあるんだなということがわかりますよね。
さて、ライセンスの話をすると決まって必ずこの2つの言葉が出てきます。
コピーライトとコピーレフトです。
両者とも似た言葉ですが、その意味と考え方は正反対でこの部分が1番重要になります。正直ライセンスの種類は二の次ですね。まずは実世界でもよく見かけるコピーライトの考え方から見ていきましょう。
©やCopyrightを見たことがあると思いますが、これがいわゆるコピーライトです。コピーライトである成果物は許可なく複製・改変・再配布・商用利用をすることはできません。行いたい場合は著作権保持者に対して許可を得ることになります。
これは私達が広く一般的に認識している著作権とその利用の関係ですね。コピーライトは付与するものではなく、この世に新しい何かを生み出した瞬間に適用されるものです。あなたが作ったモノはあなたが著作権者であり、コピーライトではないライセンスを付与しても良いわけです。
つまり、ライセンスの付与というのは能動的な選択なんですね。選択しなければあらゆるモノは基本コピーライトである。ということです。
許可なく誰でも利用してOKだけど、常にコピーレフトを継承し続ける必要があるわけですね。ここが最大の特長といえます。この特長のおかげでより自由な制作・開発環境ができ上がっていくというメリットもあったりします。
前述した通り、
でしたが、そのどちらでもない考え方がコピーセンター(Copy center /Copyfree / Permissive)です。(参考:Permissive software license)
後程登場するMITライセンスやBSDライセンスが有名で、考え方としてはコピーレフト寄りだけど元のライセンスの継承の選択が自由という特長を持っています。自由に複製・改変・再配布・商用利用ができ、またライセンスの継承も問わないことから最近ではオープンソース界隈では多く付与されつつあります。
※注釈
ちなみに制限自体が存在しないWTFPLライセンスのような考え方も存在します。(正式名称「Do
What the Fuck You Want to Public License」/日本語訳「どうとでも勝手にしやがれクソッタレ・公衆利用許諾書」)
著作権の保護が切れた著作物は基本的に法的な拘束力が消滅するわけですが、この法的に保護されていない・または保護が終わった状態のモノのことをパブリックドメインと呼びます。
誰でも自由に複製・改変・再配布・商用利用の利用ができ、唯一何にも制限を受けない状態のモノと考えると分かりやすいでしょう。
古い文学作品がパブリックドメインになっているパターンが多くありますが、実は映画や写真なども著作権保護期間の満了で誰でも自由に利用できるようになった作品もあったりします。ローマの休日などはその代表例ですね。
ちなみに、パブリックドメインであっても所有権・人格権などが侵害される場合、法域によっては利用の制限が掛かることもあります。
意外と驚いてしまう数字なんですが、ざっくり数えるだけでも140近くもの種類が存在してたりします。全てがWebに適したライセンスばかりではありませんが、如何に多種多様に発展してきたかが数字から何となく伺えますよね。(参考:Various Licenses and Comments about Them)
140全てを紹介するのは私もしんどい(笑)ですので、ここからは職種別でよく見聞きするライセンスを2、3紹介して終わりとします。普段よく利用するオーソドックスなライセンスが網羅されていますので、是非チェックしてみてください。
公式HP:https://creativecommons.org/
公式説明(日本語):https://creativecommons.jp/licenses/
ライセンスの付与の仕方:https://creativecommons.org/choose/
デザイナーの方なら必ず見ると言っても過言ではないのがCreative Commonsという団体が制定しているCCライセンスです。主にメディア系に付与される事が多いことからデザイナー・フォトグラファーなどに関係が強いライセンスの1つで、以下の4つの条件を軸に、6つの組み合わせ方が存在します。
組み合わせ方によって制限を緩くしたり、反対に強くしたりすることが容易なため付与しやすいという特徴がある一方で、必ず著作権表記(BY)が必要なため受注系のWebデザイナーとしてはなんとも使いづらいライセンスでもあったりします。
では6つの組み合わせを見てみましょう。
BY クレジット表記をすれば、改変と再配布と商用利用が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記 |
|---|---|
| 可能 | 改変、再配布、商用利用 |

BY-NC クレジット表記+非営利目的での利用なら、改変と再配布が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記、非営利目的 |
|---|---|
| 可能 | 改変、再配布 |

BY-SA クレジット表記+元のCCライセンスを継承するなら、改変と再配布と商用利用が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記、元のライセンスの継承 |
|---|---|
| 可能 | 改変、再配布、商用利用内 |

BY-NC-SA クレジット表記+非営利目的での利用+元のCCライセンスを継承するなら、改変と再配布が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記、非営利目的、元のライセンスの継承 |
|---|---|
| 可能 | 改変、再配布 |

BY-ND クレジット表記+改変をしないなら、再配布と商用利用が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記、改変の禁止 |
|---|---|
| 可能 | 再配布、商用利用 |

BY-NC-ND クレジット表記+非営利目的での利用+改変をしないなら、再配布が可能。
| 守るべき内容 | クレジット表記、非営利目的、改変の禁止 |
|---|---|
| 可能 | 再配布 |
CCライセンスでパブリックドメイン(CC0)を付与することもできる。上記の4つの条件で6通りの組み合わせ方が存在するCCライセンスですが、あらゆる権利を破棄するパブリックドメイン版(CC0)も存在します。
画像引用:cc creative commons
公式HP:http://scripts.sil.org/OFL
| ライセンス種別 | コピーレフト |
|---|---|
| 制限の緩さ(星5中) | ★★★★ |
フリーフォントなどで見かけるライセンスの1つ。一般向けのライセンスではなく、基本的にはフォントのみに付与することを目的とされています。コピーレフトですので、OFLライセンスのフォントを改変し新たなフォントを作成することもできることから、オリジナルフォントを作りやすいのも特長です。
利用条件
公式HP:https://ipafont.ipa.go.jp/
よくある質問:https://ipafont.ipa.go.jp/node87
| ライセンス種別 | OSI認定 |
|---|---|
| 制限の緩さ(星5中) | ★★★★ |
こちらもフォント向けのライセンス。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が配布したIPAフォントに付与されたライセンスで、商用利用も可能かつクレジット表記も不要なことから制限の緩いことで知られています。ただし改変し再配布する際は以下の条件があります。
改変&再配布条件
公式HP:https://opensource.org/licenses/MIT
公式説明(日本語):https://ja.osdn.net/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license
ソースコードに付与されているライセンスとしては最も制限が緩く、自由度の高いライセンスの1つがMITライセンスです。GitHubに存在するソースの中でも断トツに利用されているコピーセンターなライセンスとしても知られています。クレジット及びライセンス条項の表記(ソースに表記など)さえ行えば基本的には制限がありません。
可能なこと
| ライセンス種別 | コピーセンター |
|---|---|
| 制限の緩さ(星5中) | ★★★★★ |
公式HP:https://opensource.org/licenses/bsd-license.html
公式説明(日本語):https://ja.osdn.net/projects/opensource/wiki/licenses%2Fnew_BSD_license
MITライセンスと同じくコピーセンターなライセンス。その内容もMITライセンスとほぼ同じで、唯一違うのが書面での許可なしに著作権者及び関係する組織の名前の使用が禁止されている内容がある点です。
幾つかの種類がありますが、最も一般的な3条項が利用されるケースが多いです。クレジット及びライセンス条項の表記(ソースに表記など)さえ行えば基本的には制限がありません。
可能なこと
| ライセンス種別 | コピーセンター |
|---|---|
| 制限の緩さ(星5中) | ★★★★★ |
公式HP:http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
公式説明(日本語):http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html
「THEコピーレフト」として有名なライセンスです。WordPressを始めありとあらゆる様々なソースコードなどへ付与されていることでも知られています。
MITライセンスや修正BSDライセンスに比べると制限が強くなり、厳格にコピーレフトを守ったライセンスと認識しておくといいでしょう。
可能なこと&制限
| ライセンス種別 | コピーレフト |
|---|---|
| 制限の緩さ(星5中) | ★★★ |
GPLライセンスには制限を緩めたLGPL License(通称:LGPL)というバージョンも存在します。
LGPLライセンス条項(非公式日本語訳):https://ja.osdn.net/projects/
opensource/wiki/licenses%2FGNU_Lesser_General_Public_License_version_3.0
ざっとWeb制作でよく見るライセンス周りについて触れてみましたが、何となくライセンス周りについて見えてきたのではないでしょうか。
中々ものぐさから調べる機会が無かったりするライセンスですが、一つ一つはそこまで難しくなく要点さえ押さえておけば意外と理解しやすいものです。
頭の片隅にでも置いておいて、ライセンスについて改めてきちんと学んでみるキッカケにしてみてはいかがでしょうか!