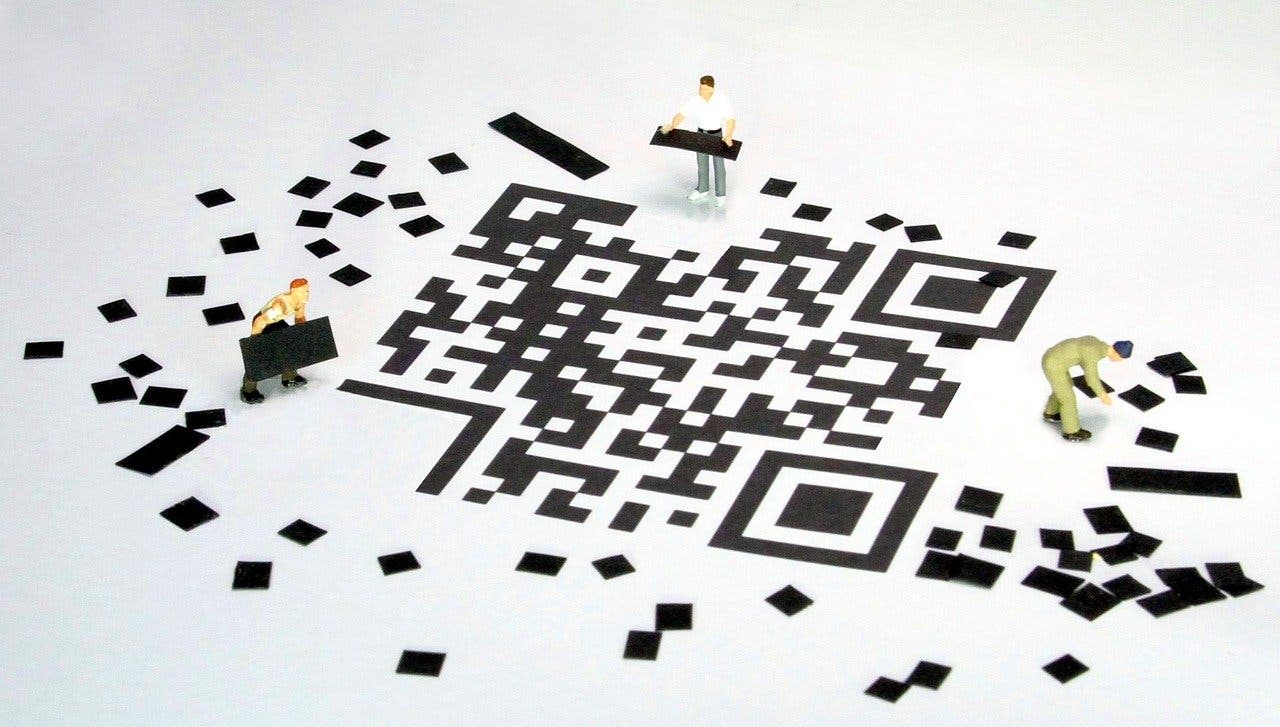
インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します
SNSマーケティング
最終更新日:2022.12.23
更新日:2024.05.07

近年、SNSで活躍するインフルエンサーを起用したPRを行う企業が増えてきました。
「インフルエンサーマーケティング」と呼ばれるこの手法。具体的に、どのような効果があげられるのでしょうか?
また、KPI設定につながる「効果が出た・出ていない」の判断は、どこを見たらよいのでしょうか?
関連記事「今さら聞けない基礎知識!インフルエンサーマーケティングとは?」
以前からインターネットのPR方法といえば、web広告が一般的でした。web広告は広告主の都合で柔軟に配信や変更、停止を行うことができ、ユーザーに直接的なアピールを行えます。
ユーザーの動向や履歴などから適切な広告を打ち出せるほか、閲覧数やクリック数、購入数などのデータが集めやすく、効果測定をしやすいのがポイントです。
ただしデメリットとして、ネット上で一様に提示されるため他社の広告と比較されてしまいやすく、広告を貼るページの訪問数が少なければ大きく機能することがありません。またクリックによる成果を見込む場合、Webサイト上の広告をクリックしないユーザーにはアプローチできないという点があります。
ユーザーの目を引くためにと、派手なバナー広告をべた貼りしたり、ポップアップ広告(ある特定のウェブページを開いた時、一番手前に自動的に表示される小さな広告枠)や自動で再生される動画広告などクリエイティブ性を打ち出したweb広告が現れましたが、これらの過剰なアピールに不快さをおぼえ、表示をブロックするユーザーが増えるという逆効果が起きています。広告の露出を増やすためにいくら費用をつぎ込んだとしてもユーザーが表示をブロックしていれば効果は見込めません。
インフルエンサーマーケティングが従来のweb広告と異なる点は、広告らしさのないアピールが可能ということです。
インフルエンサーマーケティングを行うと、インフルエンサーを支持している層からの集客が明確に期待できます。商品やサービスのPRを、広告主ではなくインフルエンサーが彼らの通常投稿と同じトーンでアップすることで、フォロワーに広告として嫌煙されずに一定数の宣伝効果を得られるのです。
さらにインフルエンサーへの好感度が高く、趣味や嗜好が似ていたり影響を受けているフォロワーが格段に多いため、特定のジャンルや年齢層に対して的確なアプローチも可能です。
インフルエンサーマーケティング「費用対効果」について知りたい方はこちら
2020年!インフルエンサーマーケティングの料金相場と費用対効果とは!
インフルエンサーが存在するのは主にSNSで、そのプラットフォームはたくさんあります。主要なSNSはInstagram、Twitter、YouTube、Facebookです。それぞれ効果を測定するには下記を指標に見て、KPI(中間目標)を設定すると良いでしょう。
インスタグラムではビジネスプロフィールを作成すると、投稿に対するアクションを確認できる「Instagramインサイト」を利用できます。たくさんの数値を見ることが出来ますが、なかでも注目したいのが
です。
特にユーザー反応数である「エンゲージメント」をみると、広告効果があるかどうかの判断に繋がります。インスタグラムは適切なハッシュタグで、狙ったユーザーに見せる工夫が効果的なSNSです。エンゲージメントをあげるにはハッシュタグを変えてみるなど施策を取ることができます。
拡散されやすく時系列順に投稿が並ぶTwitterでは、投稿するタイミングが重要になります。そこで特に注目するのが「インプレッション数」。どの時間帯だと多くの人に見られるのかを知ることで、できるだけ多くの人の目にとまるものを数多く量産することができます。
このうち「再生数」と「クリック数」が特に注目したいところ。YouTubeは動画中にURLを埋め込み、直接企業サイトや商品ページに誘導することができます。そのため、多くクリックされていれば広告効果が出ていると分かります。
以下のような課題を抱えている企業がインフルエンサーマーケティングを行うと効果が出やすいでしょう。
インフルエンサーには確実な宣伝効果があり、彼らを支持するコアなファンをゲットできる可能性があるため、上記のような課題を抱えている企業にはおススメです。
関連記事「インフルエンサーマーケティング会社22選!【2021年】注目の企業を解説」
単にインフルエンサーを起用しただけでは、マーケティングの効果を十分に得ることは出来ません。どのような準備をし、どのように実施すれば、“効果のあるインフルエンサーマーケティング“といえるのでしょうか。
具体的には、
といった6つのポイントを意識する必要があります。次項から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
関連記事>>「事例付き!インフルエンサーマーケティングの成功要素を徹底考察!」
インフルエンサーマーケティングに取り組む前に、本当にそれが自社の目的に合っているかを確認しておきましょう。例えば、商品やサービスの購入数を今すぐ増加させたい場合、インフルエンサーマーケティングよりもリスティング広告(広告サービスにお金を払い、検索結果に表示できる広告のこと。例:Google広告、Yahoo!プロモーション広告)の方が有効です。
また目的と目標は、費用対効果やインフルエンサーの起用が終了に近づいたとき、「今後も続けるべきなのか?やめるべきなのか?」の判断をするのに必要となってきます。
マーケティングの目的を設定したら、最終目標(KGI)を決め、中間目標であるKPIは前述した「効果を判断するにはどこを見たらよいのか」で紹介した部分を指標にすると良いでしょう。
商品やサービスを紹介するとき、利用するSNSで消費者へのアピール力が異なります。
例えばInstagramは写真をメインとしたSNSであるため、視覚へのアピール力が抜群にあります。お洒落なデザインや雰囲気を直感的に見せたいときなど、“視覚情報“をもとに売上を伸ばしたいときにはぴったりのプラットフォームです。またハッシュタグの拡散力が大きいため、タグ付けによるキャンペーンなどのPR方法も効果的です。
Twitterはテキストをベースとしており、“口コミ“的な情報発信に強みがあります。画像・動画を添付でき、クリックで直接飛べるURLも挿入できるなど自由度が高いうえに他のSNSよりも拡散性が高く、インフルエンサーマーケティングと非常に相性の良い媒です。若年層がプライベートで利用しているケースが多く、最新のアプリやキャンペーンをPRするのに向いています。多くの企業アカウントも登録しているので、ビジネス向けの商品やサービスとも相性が良いです。
他のSNSでも動画を投稿することは出来ますが、数十秒~2分程度。動画に特化したYouTubeにはかないません。動画は写真やテキストのみと違って直感的に「目を引く」コンテンツであり、視覚・聴覚両方に大量の情報を一気に伝えることが出来ます。そのため優れたマーケティングツールとして動画は注目されています。すでに若年層を中心にテレビよりもYouTubeをよく視聴する世代が増えており、トップYouTuberのフォロワー数は100万人を超えるケースも。芸能人と大差ないインフルエンサーが存在し、動画マーケティングに参入してみたい企業におすすめです。
どのSNSをメインに展開していくかは、自社のターゲット層や商品・サービスの特性から判断しましょう。露出させたいSNSが決まったら、そのSNS内で活躍するインフルエンサーを探すことができます。
インフルエンサーを起用するにあたって費用がかかります。
フォロワー数が多ければ多いほど影響力が大きくなるため、必要費用が大きくなっていきます。自社商品やサービスをどのくらいの範囲にわたってアプローチしていくかを決めて予算を立て、フォロワー数や影響力を比較しながらインフルエンサーをキャスティングしましょう。
フォロワー数が多いインフルエンサーを起用しても必ず効果が出るとは限りません。なぜならインフルエンサーにはすでに彼らのイメージや得意なコンテンツが存在し、それに応じたフォロワーがついています。そのため伝えたい商品やサービスと親和性の高いインフルエンサーに依頼すると、効果が出やすくなります。
インフルエンサーの得意なジャンルは、メイクアップ、スキンケア、ボディーケアといった女性に人気の商材や、スマホアプリのような若年層に人気の商材です。反対に、自動車や家電など高額な商品はインフルエンサーよりも企業ブランドの情報を消費者は支持する傾向があり、インフルエンサーと相性がよくありません。
インフルエンサーマーケティングを行う時は、インフルエンサーに合わせた商品でマーケティングを行いましょう。
SNSを使ったインフルエンサーマーケティングにおいて、投稿するタイミングはとても重要です。日常的に多くの人がSNSを利用していますが、“アクティブユーザーの多い時間帯“というものがどのSNSプラットフォームにも存在します。アクティブユーザーの多い時間にアップされた投稿は多くの人に見てもらえる可能性は高まりますが、アピールしたい商品・サービスによって最適な投稿タイミングは異なります。
例えば社会人向けの商品やサービスなどをアピールしたい場合、平日の朝か昼に投稿するのが効果的です。通勤時間やランチタイムでスマホを見る人が多いからです。
また、災害時にも関わらず大々的にPRしたり、明らかに食べきれない量の食べ物の写真を投稿すると、「常識がない」などインフルエンサーにも提携した企業にもマイナスイメージがつく可能性があります。
「炎上」という言葉があるように、拡散力の大きなSNSでは投稿内容によって非難や誹謗中傷が一気に集中する現象が頻繁に起こっています。インフルエンサーマーケティングの特徴として、広告主ではなくインフルエンサーが独自にコンテンツを作成・投稿していくため、何か間違いが起これば炎上してしまうことは容易に考えられるでしょう。投稿内容とタイミングなどについて入念に打ち合わせが必要です。
広告投稿はインフルエンサーの通常投稿と同じトーンで、わざとらしくない演出にしあがるのが理想です。インフルエンサーマーケティングが失敗するケースに、「広告主が投稿をコントロールし過ぎてしまうこと」があります。“インフルエンサーと商品が写真に写っていればよい“として投稿文などに指示を出しすぎてしまうと、インフルエンサーのフォロワーは「いつもと違う」ことを敏感に察知します。商品やサービスを購入しないことはもちろんフォローを外すこともあるため、効果を狙うのであればインフルエンサーに自由な投稿をしてもらいましょう。
また、「ステマ」という単語を聞いたことがあるかもしれません。ステマ(ステルスマーケティング)とは、企業から金銭を得ながら、宣伝であることを消費者に隠して宣伝を行うことです。いわゆるヤラセやサクラ行為と同じで、わざと消費者をだますことであり、好ましいものではありません。ステマは非常にリスクが高く、発覚すれば炎上し、ユーザーやフォロワーの信頼を失うとともに企業ブランドだけでなく業界全体の信用や売上を落とす可能性があります。
インフルエンサーマーケティングで商材をPRしてもらう際は、投稿に「#PR」のようなハッシュタグをつける“ステマ対策“を怠らないようにするのがポイントです。きちんと「広告宣伝であること」を明記している場合は、ステマではありません。
SNSで活躍するインフルエンサーが増えたことで、インフルエンサーマーケティングに乗り出す企業が増えてきました。しかしインフルエンサーマーケティングの効果を十分に発揮させるには見るべきところや気をつけるべきことがたくさんあります。十分に計画をして行うインフルエンサーマーケティングは非常に高い効果を得られるので、ぜひ今回の記事でご紹介したことを参考にしてください。